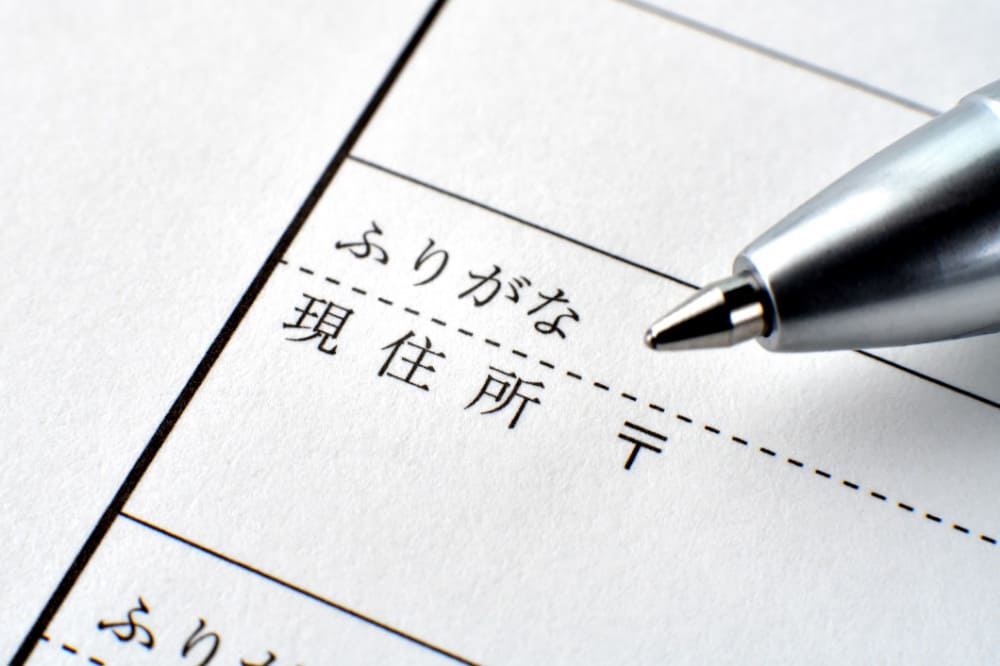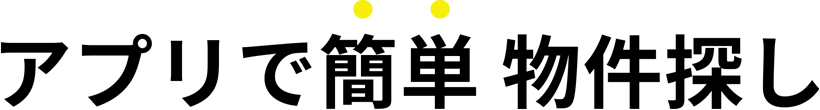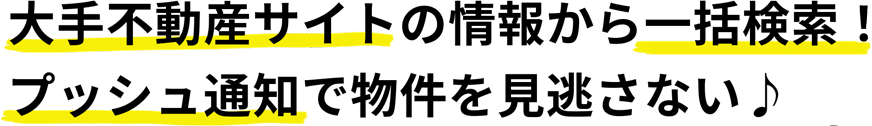住まいのコラム
引越し手続きのやることチェックリスト
順番や引越し準備のコツ
最終更新日:
 監修者
監修者
- 高野 友樹
- 公認不動産コンサルティングマスター/相続対策専門士/宅地建物取引士/賃貸不動産経営管理士
- 引越しを決めたらやることは?全体の流れは?
- やるべき手続きはたくさんありますが、「引越し先が決まったらすぐにやること」「引越し1週間前までにやること」「引越し1週間前~前日までにやること」「引越し前日にやること」「引越し当日にやること」「引越し後早めにやること」に分けられます。1つずつ行っていきましょう。
引越しが決まってから新居での生活を始めるまでには、やるべきことがたくさんあります。バラバラと進めていては効率が悪く、やり忘れも出てしまうので、リストを見ながら進めていくのがおすすめです。
この記事では、引越し前から引越し後までの各時期にやるべきことを時系列でご紹介します。チェックリストにもまとめているので、ご活用ください。
目次
引越しが決まったらやることは?チェックリストで時系列に確認

引越しが決まったら各種手続きなど、引越し前から引越し後までの各タイミングでやるべきことが決まってきます。時系列にチェックリストにまとめると下記のとおりです。
| 引越し先が決まったらやること | ||
|---|---|---|
| 1 | 現住居の賃貸契約の解約手続き・退去日の決定 | 管理会社に連絡し、解約する旨を告げて退去日を決定する |
| 2 | 現住居の駐車場の解約手続き(新居の駐車場の契約) | 駐車場に解約の連絡をする(新居での駐車場の契約をする) |
| 3 | 引越し日の決定 | 退去日をもとに引越し日を決める |
| 4 | 引越し業者の見積もり・手配 | 相見積もりを取って比較・検討し、引越し業者を選ぶ |
| 5 | 幼稚園・保育園や学校の転校手続き | 通っている園・学校で、転校のために必要な書類をもらう |
| 6 | インターネットの転居手続き | インターネット回線の住所変更手続きをする |
| 7 | 粗大ごみの処分の依頼 | 不用品を処分・売却する |
| 引越し1週間前までにやること | ||
| 8 | 梱包材の用意 | ダンボール箱などを用意する |
| 9 | 使用頻度が低いものの荷造り | 使用頻度が低いもの(本など)をダンボール箱に詰める |
| 10 | 固定電話の契約変更 | NNT東日本・NTT西日本に連絡する |
| 11 | 水道の停止手続き | 水道局に連絡する |
| 12 | 電気の停止手続き | 電力会社に連絡する |
| 13 | ガスの停止手続き | ガス会社に連絡する |
| 14 | 郵便物の転送 | 郵便局に転居届を出す |
| 15 | NHKの住所変更 | NHKに連絡する |
| 16 | 新聞の住所変更 | 新聞販売店に連絡する |
| 17 | 転出届の提出 | 役場に転出届を出す |
| 18 | 国民健康保険の資格喪失手続き | 役場で資格喪失手続きをする |
| 引越し前日までにやること | ||
| 19 | 荷造り | 荷物をダンボール箱に詰めていく |
| 20 | 新居の家具・家電のレイアウトを決定 | 新居の家具・家電をどのように配置するか、レイアウトを考えておく |
| 21 | 新居の清掃 | 荷物を運ぶ前に新居を清掃し、傷や不具合があれば撮影するなどして記録する |
| 22 | 現住居の清掃・ゴミ捨て | 退去日に向けて現住居を清掃し、不用品は計画的に処分する |
| 23 | 自分で運ぶ貴重品類の梱包 | 貴重品をバックなどにまとめる |
| 引越し前日にやること | ||
| 24 | 冷蔵庫の運搬準備 | 水抜き・霜取りをする |
| 25 | 洗濯機の運搬準備 | 水抜きをする |
| 26 | 引越し費用など現金の用意 | 引越し代など当日必要な現金を準備する |
| 引越し当日にやること | ||
| 27 | すべての荷物を梱包 | 引越し直前まで詰めていないものをダンボール箱に詰める |
| 28 | ガスの閉栓立ち会い | ガスの閉栓に立ち会う |
| 29 | 家具が運び出された後の掃除 | 家具の下のほこりなどを掃除する |
| 30 | 鍵の返却 | 管理会社に鍵を返却する |
| 31 | 新居の電気・ガス・水道の使用開始 | ブレーカーを上げるなど使用できるようにする |
| 32 | 新居の家具や家電の配置指示 | 大型家具・家電について引越し業者に配置を指示する |
| 33 | すぐ必要なものの荷ほどき | すぐ必要なもののダンボール箱を優先的に荷ほどきする |
| 引越し後早めにやること | ||
| 34 | 転入届・転居届の提出 | 役場に転入届・転居届を出す |
| 35 | マイナンバーカード、国民年金などの住所変更 | 役場で住所変更手続きをする |
| 36 | 国民健康保険の加入手続き | 役場で加入手続きをする |
| 37 | 児童・福祉関係の手続き | 役場で児童手当などの住所変更手続きをする |
| 38 | 転校の手続き | 役場と転入・転校先の園や学校で手続きをする |
| 39 | 自動車関係の手続き | 運転免許や車庫証明などの住所を変更する |
| 40 | ペットの登録 | 犬や指定動物の登録変更をする |
| 41 | 銀行口座、携帯電話などの住所変更 | 銀行口座などの各種住所変更手続きをする |
引越し先が決まったらやること
引越し先が決まったら、すぐにでもやるべきことがあります。先延ばしにしてしまうと引越しがスムーズにいかない場合もあるので、できるだけ早めに取りかかりましょう。
(1)現住居の賃貸契約の解約手続き・退去日の決定
現住居が賃貸物件であれば、退去日を決めて管理会社や大家さんに連絡し、賃貸契約の解約手続きを行います。連絡は電話でもかまいませんが、記録が残るメールや郵便、FAXなどを使うのが一般的です。
ほとんどの場合、賃貸契約には「契約を終える場合は退去の1ヵ月前に解約の通知を行う」との定めがあるので、遅くとも退去日の1ヵ月前までには、退去したい旨を連絡しなくてはいけません。期限をすぎてしまった場合は、その日数分の家賃を払わなければいけなくなる場合があります。契約によっては2ヵ月前に通知が必要なこともあるため、契約書を確認しておきましょう。
なお、退去日は自由に設定できる場合と、月末と定められている場合があります。これも、契約書に記載されています。
(2)現住居の駐車場の解約手続き(新居の駐車場の契約)
現住居で駐車場の契約をしているなら、駐車場の解約手続きも必要です。契約書で解約期限を確認した上で、早めに解約の連絡を入れましょう。特に定めがない場合は、引越しの1ヵ月前までに連絡するようにします。
新居で新たに駐車場を借りたい場合は、駐車場を探して、賃貸契約を結んでおくことも必要です。
(3)引越し日の決定
退去日を踏まえて、引越し日を決定します。引越し業者に依頼する場合、3~4月の繁忙期や土日・祝日は予約が取れなかったり、料金が割高だったりするので、引越し日の候補には平日も入れておくと安心です。
退去日と同じ日に設定し、旧居のカギを管理会社や大家さんに返却してから、新居に移動できるスケジュールにしておくとスムーズです。
(4)引越し業者の見積もり・手配
複数の引越し業者から見積もりを取り、引越し業者を予約します。早めに予約したほうが日程や時間の自由がききやすく、引越し費用も安くなりやすいので、引越し予定日の2ヵ月~1ヵ月半前に取りかかるのがおすすめです。見積もりを比較・検討して、業者を選びましょう。
(5)幼稚園・保育園や学校の転校手続き
子どもがいる場合は、転園や転校の手続きが必要です。
・幼稚園
転園先候補の幼稚園をいくつか選んで、それぞれ定員に空きがあるか、入園可能かを確認します。転園先が決まったら、現在通っている園の在園証明書や転園先の入園願書、住民票などを準備して、手続きを行います。年度の途中での転園も可能です。
今通っている幼稚園には、転園の1ヵ月前までに退園する旨を伝え、転園先に提出するための在園証明書の発行を依頼しておきます。
・保育園
希望する園に空きがある場合は、転園申込書のほか、保護者の就労証明書など、引越し先の自治体が求める書類を提出して手続きを行います。今通っている保育園には、提出期限までに退園届や転園届を提出します。
なお、引越し前に認可保育園に入園の申込みをする場合は、管外協議(住民票のない市区町村への斡旋という特別な扱い)となり、入園選考で減点対象になるなど入園のハードルが上がるため、引越し後に入園申込みをするのもひとつの手です。また、自治体によっては、管外協議扱いにならない救済措置をとっているところもあります。
・学校
公立の小学校・中学校は、引越し先が同一市区町村内か他市区町村かで少し手続きが異なります。
同一市区町村内の場合は、在学校に転校する旨を伝えた後、新しく通う学校に連絡。引越し後に市区町村役場に転居届と在学証明書を提出して転入学通知書をもらい、転入先の学校に提出する流れになります。
他市区町村の場合は、在学校に転校する旨を伝えた後、新住所地の教育委員会に連絡して通学指定校を確認。転校手続きの日程を転入先の学校と相談します。現住所の役場に転出届を出して転出学通知書を発行してもらい、在学中の学校にこれを提出して、在学証明書と教科用図書給与証明書をもらいます。引越し後に、転入先の役所に転入届を出して入学通知書をもらい、ほかの2枚の証明書と一緒に転入先の学校に提出する流れです。
(6)インターネットの転居手続き
インターネットを新居ですぐに使用したい場合は、回線工事などが必要となり、時間がかかる可能性があるため、転居日の2ヵ月~1ヵ月半前に済ませておくのがおすすめです。
現在使用中の回線を継続する場合は、住所変更手続きを行います。新しく契約する場合は、現在の回線の解約手続きと、新しい回線の新規契約手続きを行います。
(7)粗大ごみの処分の依頼
不要品は引越し前に処分しておけば、引越しの荷物も少なくなります。自治体の回収サービスのほか、回収業者を利用する、買い取りショップなどに売却する、ネットオークションやフリマアプリなどを利用して販売するといった方法もあるので、状況に応じて使い分けましょう。
自治体の粗大ごみ回収サービスは予約制で、直近では予約が取れないこともあるので、処分は余裕を持って行うことをおすすめします。

引越しに伴う手続きは多岐に渡ります。引越しが決まったらまずは優先度をつけて、やるべきことをリスト化していきましょう。特に、今の住居の解約通知を忘れてしまうと、その分余計な日割家賃が発生することもありますので素早く行うのがおすすめです。
引越し1週間前までにやること

ライフラインの住所変更など、引越し1週間前までに完了させておきたいことも複数あります。直前に慌てないよう、確認しておきましょう。
(8)梱包材の用意
荷造りに備えて、ダンボール箱やガムテープ、緩衝材などの梱包材を用意します。引越し業者を予約している場合は、業者が無料で提供してくれることもあります。ただし、一定数以上は追加料金がかかる業者もあるので、事前に確認しておきましょう。
(9)使用頻度が低いものの荷造り
荷造りは、使用頻度が低いものから進めていくとスムーズです。シーズン外の服、靴、布団、電化製品、非常用の食品、あまり使われていないおもちゃ、本、日用品のストックなど、しばらく取り出せなくても生活に支障がないものからダンボール箱に詰めていきます。
運びやすさを考えて、本などの重たいものは小さめのダンボール箱に詰めます。ダンボール箱には、マジックなどで内容物と新居のどこに運ぶのかを明記しておきましょう。荷造りの過程で不要と判断した本や衣類、おもちゃなどは、買い取りに出すなどして処分します。
荷造りを始めると、処分すべき不用品が出てきたり、梱包材が足りなくなったりしがちなので、荷造りは少なくとも引越し予定日の2週間前には取り掛かるのがおすすめです。荷物が多い場合は、もう少し前から始めましょう。
(10)固定電話の契約変更
固定電話がある場合は、移転手続きが必要です。局番なしの「116」に電話するか、引越し先を対象エリアとするNTT東日本またはNTT西日本の公式サイト上で手続きを行います。
(11)水道の停止手続き
現住所を管轄する水道局に連絡して、水道の停止手続きを行います。住所や氏名、引越し予定日、お客様番号などが必要になるので、検針票を準備しておきましょう。
同時に、新居を管轄する水道局に連絡して入居日を伝え、開始手続きも行っておきます。
(12)電気の停止手続き
新居でも同じ電力会社を使う場合は、契約する電気会社に連絡して、現住所の電気の停止と新居での使用開始をまとめて申し込みます。電気会社を変える場合は、別々に電気の停止と新規契約の手続きが必要です。インターネット上または電話での手続きになります。
(13)ガスの停止手続き
電気と同様に、新居でも同じガス会社を使う場合は、契約するガス会社に連絡をして、現住所のガスの停止と新居での使用開始をまとめて申し込みます。ガス会社を変える場合は、別々にガスの停止と新規契約の手続きが必要です。
(14)郵便物の転送
郵便局に転居届を出しておくと、届出日から1年間、旧住所宛の郵便物などを新住所に無料で転送してくれるので便利です。郵便局窓口などに設置されている転居届に必要事項を記入して、窓口に提出またはポストに投函するか、インターネット上で手続きをします。
(15)NHKの住所変更
世帯全体で引っ越す場合は、NHKの住所変更が必要です。NHKの公式サイトまたはNHKふれあいセンター(フリーダイヤル:0120-151515)から手続きできます。
(16)新聞の住所変更
新聞をとっている場合は、配達してもらっている販売店に連絡し、配達先住所を変更してもらいます。新聞によっては、公式サイト上での手続きも可能です。
一部地域で発行されている新聞の場合、引越し先ではとれない場合もあるので、まずは販売店や公式サイトなどで確認しましょう。
(17)転出届の提出
新居の場所が旧住所とは別の市区町村の場合、引越し日の2週間前~引越し日に役場で転出届を提出して、転出証明書を受け取ります。同じ市区町村内での引越しの場合、転出届の提出は不要です。
(18)国民健康保険の資格喪失手続き
国民健康保険に加入している場合は、資格喪失または住所変更の手続きが必要になります。新居が旧住所とは別の市区町村の場合は、まず旧住所の役場で資格喪失手続きを行い、引越し後に新居の役場で加入手続きを行います。
資格喪失手続きは、転居後14日以内に行うものとされていますが、引越し日より前でも手続きできるので、転出届を提出する際に一緒に行っておくのがおすすめです。

ライフラインの変更・停止手続きなどは細かなものが多く、後回しにしがちです。手続きをする先によっては平日の日中しか問い合わせを受け付けていないこともあります。あらかじめ時間に余裕を持って手続きを進めておきましょう。
引越し前日までにやること
引越しの1週間前~前日には、引越しをスムーズにするために必要なことを行っていきます。引越し当日に向けてやることを確認しておきましょう。
(19)荷造り
引越し直前の荷造りでは、事前に梱包できなかったものを「よく使うもの」「毎日使うもの」「引越し当日の朝まで使うもの」の3グループに分けて、ダンボール箱に順番に詰めていきます。
・よく使うもの
シーズンの洋服や靴、学校で使う教科書、調理器具などは、引越し数日~2、3日前に「これだけあればなんとかなる」分を残して箱詰めします。
・毎日使うもの
引越し前日まで使う調理器具や食器、仕事道具などは、引越し前日に箱詰めします。
・引越し当日の朝まで使うもの
洗面用具や携帯電話の充電器、タオルなど、引越し当日の朝まで使うものは、専用の箱を用意して最後に箱詰めします。新居でもすぐに必要なものばかりなので、わかりやすいようにダンボール箱に印をつけておくのがおすすめです。
引越しまでに使うかもしれないものをひとまず箱詰めする際は、ダンボール箱の蓋は開けたままで、必要になったらいつでも取り出せるようにしておきます。取り出して使い終わったらまた箱に戻し、引越し当日に蓋をします。
(20)新居の家具・家電のレイアウトを決定
家具・家電のレイアウトをあらかじめ決めておけば、新居で引越し業者への指示が出しやすく、搬入作業がスムーズになります。
特に、ベッドや冷蔵庫、テレビなどの大型家具は、後から自分で動かすことが難しいので、先に置き場所を決めておきます。
(21)新居の清掃
引越し前に新居を掃除しておくと、気持ち良く入居できます。部屋の傷や不具合を見つけたら撮影しておくと、後の退去時に修繕費を請求されても、入居前からの傷や不具合であることを証明できます。
大きな不具合が見つかったら、その時点で管理会社や大家さんに連絡しましょう。
(22)現住居の清掃・ゴミ捨て
賃貸物件の入居者は、退去の際に原状回復を行う義務があります。経年劣化による変化は対象外ですが、浴室のカビや部屋の汚れなどは、そのままにしておくと原状回復のコストがかかります。退去費用として請求され、敷金からの返金が少なくなってしまう、もしくは追加で支払いが発生してしまうので、水回りや汚れが目立つ箇所は、しっかりと掃除しておくことをおすすめします。
掃除や荷造りの過程で出たゴミは、自治体のルールに沿って処分します。ゴミの種類によって回収日が決まっているので、計画的に処分していくことが大切です。
(23)自分で運ぶ貴重品類の梱包
現金や預金通帳、貴金属、印章などの貴重品は、引越し業者に運んでもらうことができないので、自分で運ばなくてはいけません。忘れず持っていけるように、鞄などにまとめておきます。

引越し日直前の1週間はやるべきことが多くてバタバタしてしまいがちです。何かイレギュラーのことが起きてしまうと準備が間に合わないというリスクもあります。そのため、1週間前までに済ませられるものがあれば、早めに終わらせておくと安心でしょう。
引越し前日にやること
引越し前日は、大型家電を運搬するための準備や引越し代金の支払準備を行います。準備を怠ると家電の故障にもつながるため、忘れずに行いましょう。
(24)冷蔵庫の運搬準備
冷蔵庫は運搬中の水漏れを防ぐために、2~3日前に給水タンクの水を捨てて製氷機能を止め、前日には中身を空にしてコンセントを抜いておきます。翌日朝に、庫内のついた水気を拭き取り、蒸発皿に溜まった水を捨てます。
(25)洗濯機の運搬準備
運搬中の水漏れを防ぐために、前日に給水ホース・排水ホースに溜まった水を抜き、蛇口との接続パーツやホースを取り外しておきます。取り外した部品はなくならないように、洗濯槽に入れてテープなどで固定しておくのがおすすめです。
(26)引越し費用など現金の用意
引越し代は、業者が作業を開始するときか作業終了後に、現金で支払うのが一般的です。お釣りのないように、現金を用意しておきます。

入居前からもともと住居についていたもの(たとえば一部の家具やカーテンなど)がある場合は、オーナーや大家さんの持ち物なので、引越し業者が間違って持っていかないように注意が必要です。特に洗濯機のエルボ(排水管と排水ホースを繋ぐL字の部品)など、間違えやすいものには気をつけましょう。
引越し当日にやること

引越し当日は、旧居と新居の両方でやることがあります。当日は慌ただしくなりがちなので、事前にやることを確認しておきましょう。
(27)すべての荷物を梱包
当日の朝まで使っていた物を含め、すべての荷物をダンボール箱に詰めて蓋をします。箱に内容物の名称と搬入先が書かれているか、もう一度確認しておきましょう。
(28)ガスの閉栓立ち会い
ガス会社やガスメーターの位置によりますが、ガスの閉栓立ち会いと料金精算が必要になる場合があります。事前にガス会社に確認し、必要があれば引越し当日に立ち会いを行います。
(29)家具が運び出された後の掃除
引越しの荷物が搬出された後に、一通り掃除を行います。そのため、必要な掃除道具はダンボール箱に詰めずに残しておきましょう。大型家電や家具の裏など、搬出前には掃除しきれなかった場所を中心にきれいにしておきます。
(30)鍵の返却
旧居の掃除が終わったら、管理会社や大家さんに鍵を返却します。退去時の立ち会いがある場合はその場で直接手渡し、立ち会いがない場合は管理会社へ持っていく、郵送する、施錠後にポストに入れておくといった方法がとられます。鍵の返却方法は、事前に管理会社や大家さんに確認しておきましょう。
(31)新居の電気・ガス・水道の使用開始
電気のブレーカーを上げ、水道の元栓を開けて使用できるようにします。ガスは業者の立ち会いのもとで開栓します。
(32)新居の家具や家電の配置指示
引越し先には、業者より早く到着するのが理想です。家具の搬出後の掃除や旧居の立ち会いなどを考えると、家族や同居人、引越しを手伝ってくれる人と手分けして行うのが現実的です。
大型の家具・家電の位置は後から変えるのが大変なので、荷物の搬入の際は、どこに何を、どの向きに置くのか、明確に指示します。
(33)すぐ必要なものの荷ほどき
荷物の搬入が終わったら、引越し初日から必要なものをダンボール箱から出していきます。荷ほどきは一度にやろうとせず、まずは最低限必要なものから始めましょう。

引越し先がマンションの場合、引越し業者のトラックを駐車する場所がマンションの規定で決まっていることがあります。知らずに自由に止めてしまうと、近隣住民とのトラブルになるリスクもあります。新居の規定などはあらかじめ確認しておき、スムーズに引越しを行いましょう。
引越し後早めにやること
引越しが完了したら、新居での生活のために必要な手続きを進めていきます。引越しから2週間以内など、期限がある手続きもあるため注意しましょう。
(34)転入届・転居届の提出
引越しから2週間以内に役場へ行き、ほかの市区町村から移ってきた場合は転入届、同じ市区町村内の引越しの場合は転居届を提出します。
(35)マイナンバーカード、国民年金などの住所変更
マイナンバーカードや国民年金などの住所変更を行います。転入届または転居届の提出と一緒に行うといいでしょう。
(36)国民健康保険の加入手続き
国民健康保険に加入する場合は、住所地の役場で加入手続きを行います。転入届または転居届の提出と一緒に行うのがおすすめです。
(37)児童・福祉関係の手続き
引越しで市区町村が変わった場合は、住居地の役場で引越し後15日以内に児童手当などの住所変更手続きが必要です。
(38)転校の手続き
引越し前の園や学校から受け取った書類を提出して、保育園や幼稚園、小学校・中学校などの転園・転校手続きをします。
(39)自動車関係の手続き
車庫証明や車検証、運転免許証などの住所変更手続きのほか、管轄の陸運支局が変わった場合は、ナンバープレートの変更が必要です。車庫証明は新居の住所を管轄する警察署の窓口、運転免許証は警察署や運転免許更新センター、車検証やナンバープレートは普通車なら管轄の運輸支局での手続き、軽自動車なら軽自動車検査協会での手続きになります。
(40)ペットの登録
ペットに犬や指定動物を飼っている人は、役所または保健所の窓口で登録変更手続きを行います。登録料がかかる場合もあります。
(41)銀行口座、携帯電話などの住所変更
銀行口座や携帯電話、各種保険、クレジットカード、勤務先などの住所変更手続きをします。重要な通知が届かないことのないように、早めに変更しておきましょう。また、ECサイトや宅配サービスなどの住所変更も忘れずに行います。

たとえば住民票の移動は、住民台帳基本法で義務化されている手続きです。決して後回しにせず、しっかり手続きを完了させましょう。平日の日中でないと行えない手続きもあるので、仕事の調整をあらかじめつけておくなど、事前準備が大切です。
まとめ
引越し前後にやるべきことは多く、忘れてしまうと新居での生活に影響が出るものが多くあります。しかし、忙しいとつい後回しにしてしまいがちです。
時系列のチェックリストで事前に全項目を確認し、漏れがないようチェックしながら引越し準備を進めましょう。
監修者プロフィール
 監修者
監修者
- 高野 友樹
- 公認不動産コンサルティングマスター、相続対策専門士、宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士
不動産会社にて600件以上の仲介、6000戸の収益物件管理を経験した後、物流施設に特化したファンドのAM事業部マネージャーとして従事。現在は株式会社高野不動産コンサルティングを設立し、不動産コンサルティングを行う。