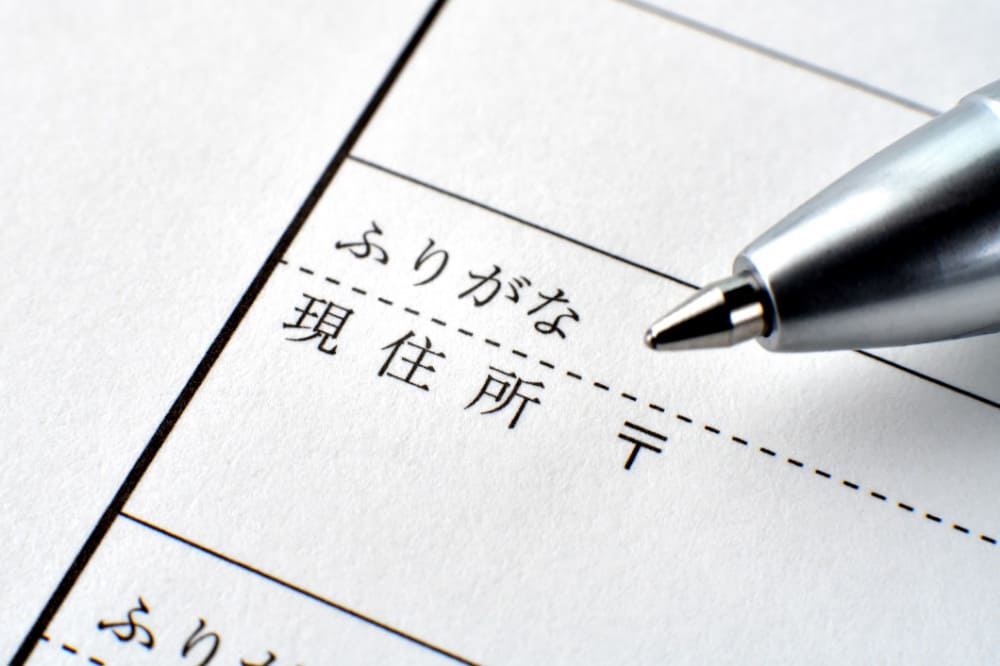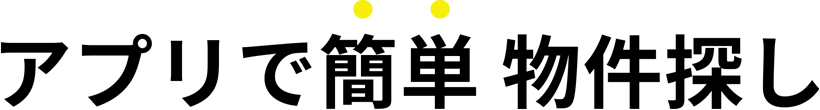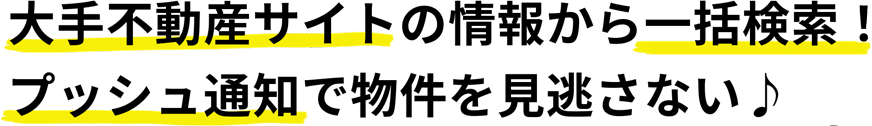住まいのコラム
転出届の期限はいつからいつまで?
必要なものや手続き方法を解説
最終更新日:
 監修者
監修者
- 矢野 翔一
- 2級ファイナンシャルプランニング技能士(AFP)、宅地建物取引士、管理業務主任者/有限会社アローフィールド代表取締役社長
- 転出届はいつまでに提出しなければならない?
- 転出届は、異なる市区町村へ引越ししてから14日以内に提出する必要があります。転出届の提出が遅れても罰則はありませんが、転居後14日内に転入届を提出しなければ5万円以下の過料が科せられるおそれがあります。転入届の提出には転出届が必要ですので、余裕を持って転出届を提出しておきましょう。
転出届は、異なる市区町村へ転居する際に転出元の役所へ提出する書類です。住民票は市区町村単位で管理されているため、転居時には転出元から住民票を抜く手続きが必要になるのです。
ここでは、転出届の提出期限と手続き方法を解説します。引越し前に慌てないよう、手続きの方法と期限を学んでおきましょう。
転出届の提出期限はいつからいつまで?

転出届の提出期限は、原則として引越しした当日から14日後までの提出を求められます。仮に8月1日に引越しを済ませたなら、14日後の8月15日までに書類を提出しなければなりません。
転出届の出し方
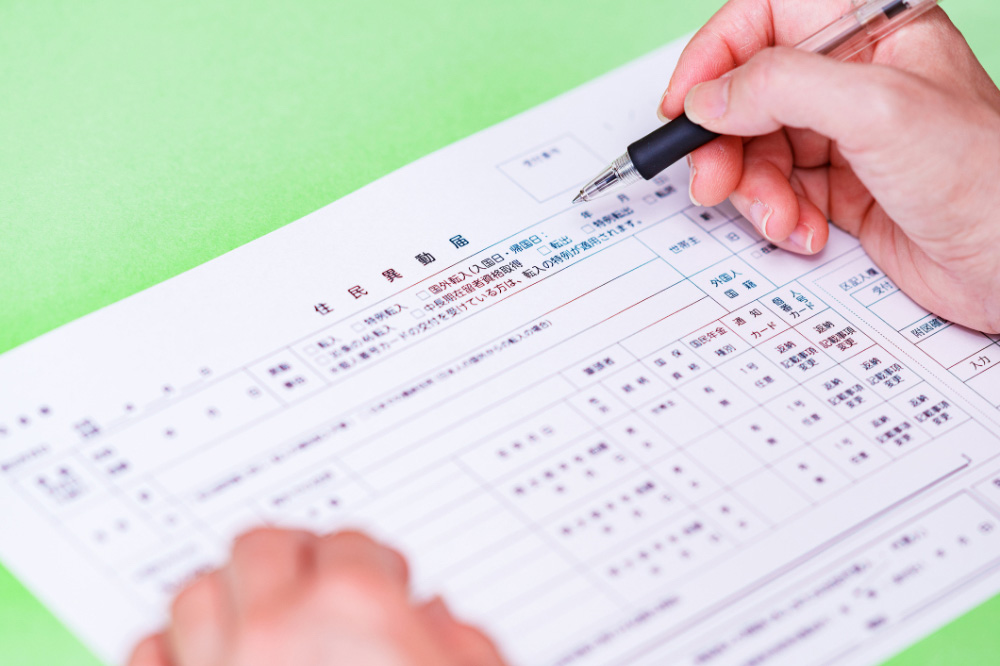
転出届は現在居住している市区町村の役所へ提出する書類です。提出方法は役所窓口、オンライン、郵送の3種類があります。それぞれ手続きに必要な時間や手間が異なるため、引越しのスケジュールに合わせて適切な方法を選びましょう。
必要なもの
転出届を提出する際には、いくつかの必要書類があります。
・本人確認書類
※運転免許証、各種保険証、パスポート、在留カードなど
・国民健康保険証
※加入者のみ
・印鑑登録証
※登録している方のみ
・マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード
※交付を受けている方のみ
すべての手続き方法で上記の書類全部が必要になるわけではありませんが、手続き前には一通りの書類が揃っているように準備しておくとよいでしょう。
役所窓口での手続き方法
転出・転入の手続きに使用する「住民異動届」に必要事項を記入し、書類上部にある「転出届」にチェックを入れましょう。
転出届の手続きは、転居元になる市区町村役所が窓口です。転出届を窓口に提出する際、本人確認書類の提出が求められます。公的機関で発行された本人確認書類ならば問題ありませんが、転居前の住所と顔写真を同時に確認できるよう、運転免許証や運転経歴証明書の提出が望ましいでしょう。
また、国民健康保険に加入している人は、転出に伴う資格喪失の手続きも同時に行っておきましょう。手続きは有効期限が残っている国民健康保険証を提出するだけです。
印鑑登録も転出と同時に抹消する必要がありますが、こちらも印鑑登録証を提出するだけです。忘れずに手続きを行っておきましょう。
なお、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを提出すれば、転出に関する手続きを一括して行ってもらうことができ便利です。
一通りの手続きが完了した後は、窓口から「転出証明書」が発行されます。転出証明書は転入手続きに必要な書類なので、忘れずに受け取っておきましょう。
郵送で手続きする場合
転出元の市区町村のホームページから住民異動届をダウンロードし、プリントアウト後に必要事項を記入して転出届を作りましょう。
郵送時には窓口での手続きと同様に、本人確認書類の提出が必要です。原本を送る必要はなく、運転免許証やマイナンバーカード等のコピーの送付で問題ありません。
転出届および本人確認書類のコピーが用意できたら、転出元の市区町村役所の担当窓口に郵送してください。その際、転出証明書の返送に使う84円切手が貼られた封筒も同封するのを忘れずに。
なお、国民健康保険の資格喪失手続きは郵送には対応していません。国民健康保険加入者は郵送だけでは転出の手続きを完了できないので、市区町村役所の窓口または「マイナポータル」上から手続きを行いましょう。
また、一部の市区町村では転出と同時に印鑑登録が自動的に抹消されます。しかし転出元の市区町村が自動抹消をしてくれるとは限らないため、事前に市区町村のホームページなどで確認し、必要に応じて窓口またはマイナポータルで抹消手続きを行いましょう。
オンラインで手続きする場合
転出届の発行手続きはオンラインでも行えます。オンライン手続きの窓口は「マイナポータル」にあり、事前にマイナンバーカードの発行とマイナポータルの利用者登録が必要です。
マイナポータル内の「注目の情報欄」から「引越しの手続」ボタンをタップし、ガイドに従って手続きを進めてください。
手続きの途中でマイナンバーカードの読み取りを求められます。読み取りに対応したスマートフォンまたはICカードリーダーを備えたパソコンを用意しておきましょう。
自治体によっては国民健康保険および印鑑登録抹消の手続きもマイナポータル上から行えます。ただし、すべての自治体がマイナポータルでの手続きに対応しているわけではないので、手続きの前には自治体のホームページを確認しておきましょう。

マイナポータルはパソコンやスマホから利用者登録できます。基本的には24時間利用できますが、メンテナンス作業で利用できない可能性があるため、余裕を持って利用者登録や手続きを済ませましょう。
転出届を出したら引越し先で転入届を出そう

転出届を提出しただけでは、住民票の移動は完了していません。受け取った転出証明書を転入先の市区町村役所に提出し、転入先の住民票ができてはじめて手続きが終わります。転出届と同様に、転入届を提出するための期日もあるので、忘れずに期日内に役所で手続きを行いましょう。
転入届の出し方については「住民票の移し方は?転出届・転入届・転居届の出し方を解説」をご覧ください。
期限内に転出届を出さなかったらどうなる?

転出届は、新たな市区町村へ転入した日から14日以内に提出をしなければ、住民基本台帳法に基づき罰則を受ける恐れがあります。
住民基本台帳法第22条では、転入をした日から14日以内に転入届を市区町村長に届けることを義務づけており、正当な理由がなく届出をしない場合には5万円以下の過料が科せられる可能性があります。
転出届の提出期限には法的な期限は定められていませんが、転入届を出すためには転出届により発行される転出証明書が必要であるため、転入当日から14日以内に転出の手続きも行わなければなりません。
転出届は転出する以前にも提出が可能ですので、引越し日が迫る前に手続きを進めておきましょう。
転出届が不要なケースとは?

転出届は、引越しを行う時に必ず提出が求められるとは限りません。次のようなケースでは、転出届に関する手続きは不要です。
同じ市区町村内での引越し
現在の住所と引越し先が同じ市区町村である場合、住民票がある市区町村からの転出はないため、転出届の提出は不要です。
ただし、市区町村に登録する住民票は新しい住所に書き換える必要があり、「転居届」という別の書類を提出します。転居届は転出・転入の手続きを同時に行えるので、別途転入届を提出する必要はありません。
なお、国民健康保険および印鑑登録の手続きも、同一市区町村内であれば転居届だけで同時に行えます。ただし、旧住所が記載されたままの国民健康保険証と印鑑登録証明書は使用できませんので、新たに新住所が記載されたものの発行を受けましょう。
単身赴任する場合
単身赴任による転居においては、転出届の提出が不要になる場合があります。遠方の赴任先に単身用の住まいを構える場合でも、生活の拠点を現住所に残しておく場合には、転出および転入の手続きをする必要はありません。
ただし、赴任先で行政サービスを受ける必要がある場合には、転出・転入の手続きを行い住民票を移さなければなりません。その際、単身赴任者が現住所における世帯主であるならば、現住所の市区町村に世帯主変更届を提出し、世帯主を変更する手続きも必要です。
海外へ転居する場合は「海外転出届」を提出
1年以上に渡り海外へ転居する場合には、転出届ではなく「海外転出届」を提出する必要があります。海外転出届を市区町村へ提出すると住民票が除票扱いになり、日本国内の住民ではなくなります。住民税が課税されなくなるので、海外への転出時には忘れずに手続きを行いましょう。
本人が手続きを行う際に必要な書類は、運転免許証やマイナンバーカード等の本人確認書類のみです。なお、手続き後にはマイナンバーカードや国民健康保険証、印鑑登録証など市区町村にひも付く書類を返却しなければなりません。手続きを行う際には忘れずに該当の書類を用意しておきましょう。

短期の住み込み、一時的な転居のように主な生活拠点が変わらないようなケースにおいても転出届の提出が不要となる可能性があります。
まとめ
転出届は、異なる市区町村間で引越す際に必ず提出しなければならない書類です。
新たな市区町村への引越し後、14日以内に転入の手続きを行えない場合は過料が科せられる恐れがあります。転入手続きには転出届の提出が必要なため、転出の手続きは忘れないように注意しましょう。
なお、引越しをしたら必ず転出届を提出しなければならないわけではありません。単身赴任では提出の必要がなく、長期の海外転居の場合は海外転出届が必要です。転居の理由によって提出の有無が変わりますので、提出の必要があるのかわからない場合には、市区町村役所の窓口に相談してみましょう。
監修者プロフィール
 監修者
監修者
- 矢野 翔一
- 関西学院大学法学部法律学科卒業。有限会社アローフィールド代表取締役社長。保有資格:2級ファイナンシャルプランニング技能士(AFP)、宅地建物取引士、管理業務主任者。
不動産賃貸業、学習塾経営に携わりながら自身の経験・知識を活かし金融関係、不動産全般(不動産売買・不動産投資)などの記事執筆や監修に携わる。