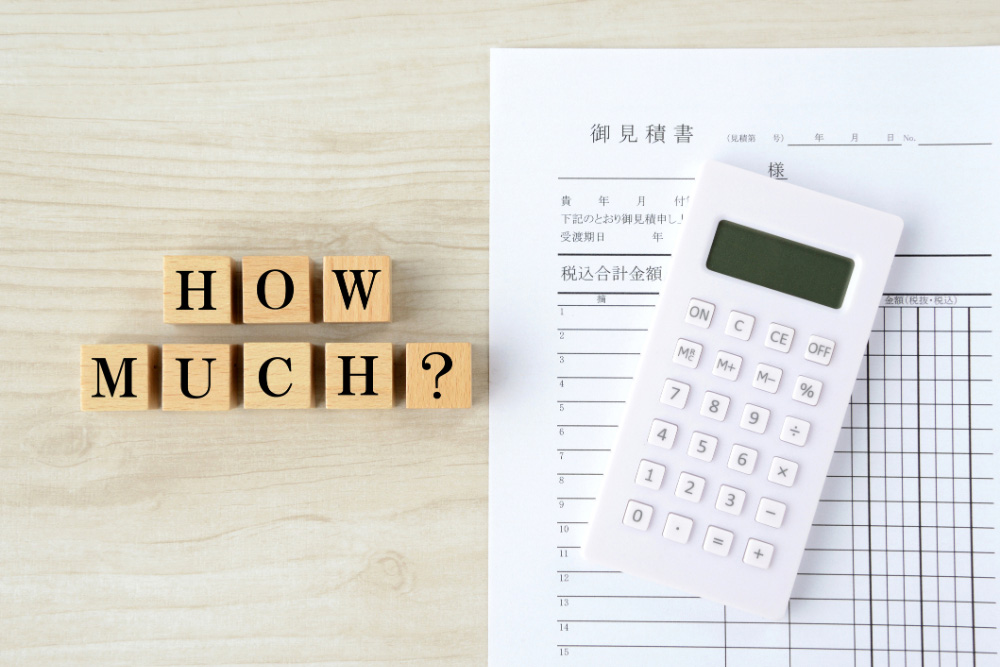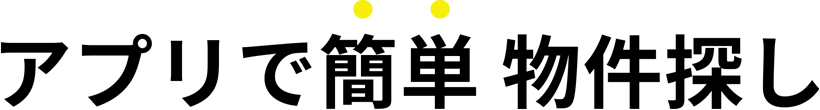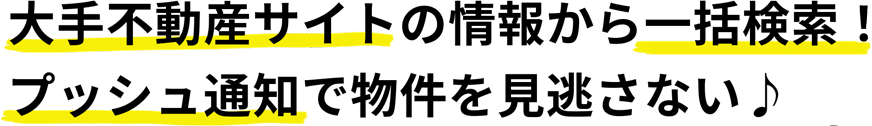住まいのコラム
引越しの初期費用の相場は?
払えないときの対処法とは
最終更新日:
 監修者
監修者
- 亀梨 奈美
- 不動産ジャーナリスト/株式会社real wave代表取締役
- 引越しの初期費用はどれくらいかかるもの?
- 引越しにかかる初期費用は、入居先の家賃の5~6ヵ月分といわれています。内訳の中で高額かつ変動しやすいのが敷金・礼金・仲介手数料です。一般的にはそれぞれ家賃の1ヵ月分に設定されていますが、敷金・礼金は大家さんの意向によっては2ヵ月分以上に設定されることもありますので、物件選びの際には注意しておきましょう。
賃貸物件への引越しをする際に、気をつけておかなければならないのが初期費用の金額です。敷金や礼金、引越し代金などまとまった出費が発生するため、引越しのたびに貯金の大半を使うという人も少なくありません。
引越しを計画するときには、どの程度の初期費用を見込んでおけばよいのでしょうか。今回は引越しにかかる初期費用の相場と、資金が足りないときの対処法についてご紹介します。
引越しの初期費用の内訳と相場

引越しにかかる初期費用は、一般的に以下の費用を指します。
・敷金
・礼金
・仲介手数料
・前払い賃料
・保証料
・火災保険料
・引越し費用
ここでは初期費用の内訳と、それぞれの相場をご紹介します。
敷金/ 家賃の1~2ヵ月分
敷金とは、入居者(借主)が入居時に大家さん(貸主)へ支払うお金の項目のひとつです。家賃の未払い分への補填や、退去時の原状回復費用に充てられる預かり金としての性質を持ち、使用されなかった分の残額は退去時に借主へ返還されます。
国土交通省住宅局が発表した「令和4年度住宅市場動向調査報告書」によれば、令和4年に契約が決まった世帯のうち、敷金を預けた世帯は58.7%と、全体の約6割を占めました。近年は敷金ゼロの物件も多く登場していますが、まだまだ敷金の支払いが必要な物件は多いため、家賃の1~2ヵ月分程度を用意しておけると安心です。
敷金について、詳しくはこちらの記事をご覧ください。
敷金とは?礼金との違いや返金の有無、なしの場合のデメリットを解説
礼金/ 家賃の1~2ヵ月分
礼金とは、入居者が大家さんへ支払う項目のひとつです。家を貸してもらう大家さんへのお礼金であり、敷金のように入居者が与えた過失・損耗に対する補填には使われず、退去時の返還もありません。
「令和4年度住宅市場動向調査報告書」によれば、令和4年に契約が決まった世帯のうち、礼金を支払った世帯は44.8%に留まりました。相場は家賃の1~2ヵ月分ですが、近年は礼金を無料にする物件が徐々に増加する傾向が見られます。今後は少子高齢化の進行により、今よりも入居者募集競争が激化することが予想されるため、礼金を無料化する物件はさらに増えていくでしょう。
礼金について、詳しくはこちらの記事をご覧ください。
礼金とは?敷金との違いや金額相場、交渉のポイントを簡単に解説
仲介手数料/ 家賃の1ヵ月分
仲介手数料は、賃貸物件の仲介役となった管理会社に支払うお金です。管理会社が徴収できる仲介手数料は、宅地建物取引業法において上限が家賃1.1ヵ月分までと定められているため、請求額は最大でも家賃1ヵ月分+消費税に留まります。
仲介手数料について、詳しくはこちらの記事をご覧ください。
仲介手数料の相場は?計算方法や賃貸の初期費用を抑えるコツを解説
前払い賃料/ 家賃の1ヵ月分
賃貸借契約においては、入居月の日割分および翌月の家賃を契約時に支払う風習があります。たとえば4月10日に4月16日から住み始める契約を結んだ場合、10日の時点で4月分(15日分)と5月分(1ヵ月分)の合計1.5ヵ月分の家賃支払いを請求されます。
最近は入居直後の家賃を無料化するフリーレントを導入する物件が増えていますが、礼金を無料化する物件ほど多くはありません。今後も多くの物件で賃料の前払いが求められると予想されるので、前払い分として家賃1~2ヵ月分程度の初期費用は確保しておきましょう。
保証料/ 家賃の1ヵ月分
賃貸借契約時に家賃保証会社を利用する場合、保証会社に保証料を支払う必要があります。保証料は契約時に家賃の1ヵ月分程度が請求され、退去まで家賃の滞納がなく保証会社を利用しなくても返金はありません。
保証会社によっては保証料を毎月の家賃に上乗せして徴収する場合があります。徴収方法は会社によって異なるうえ、管理会社が指定した保証会社を任意で変更することはできないので、賃貸借契約を結ぶ前に保証料の支払い方法と金額を確認しておきましょう。
火災保険料/ 1.5〜2万円程度
多くの賃貸物件では、賃貸借契約時に火災保険への加入を義務づけています。保険料は入居時に契約期間(2年間)分を一括で支払うのが一般的であり、多くの保険会社は保険料を1.5〜2万円程度に設定しています。
なお、火災保険は必ずしも管理会社が指定した保険会社と契約する必要はありません。自分で探した保険会社の保険料が安ければ、契約先を任意で変更することが可能です。ただし、管理会社指定の保険会社を使わない際には、保険の加入証明を管理会社に提出する必要があります。また、大家さん側が火災保険でカバーできる損害の種類を指定する場合があるので、指定以外の保険会社を利用する場合には、管理会社に要件を確認しておくとよいでしょう。
引越し費用/ 数万〜数十万円程度
荷物の運搬を引越し業者に依頼する場合には運搬料がかかります。
関東運輸局が発表した「引越しのモデル運賃・料金」によれば、100km程度の移動を含む8時間以内の作業の場合、単身者なら5~6万円、家族連れなら10~20万程度の基本料金が必要です。さらにピアノや乗用車の運搬、冷暖房器具の付け外しといった追加作業があると、作業内容に応じた費用が加算されます。
毎年2月~4月の繁忙期に引越しを依頼する場合、割増料金を追加される場合があります。さらに繁忙期は他の時期の数倍の引越し依頼が集中するため、指定した日程で引越しを受けてもらえないこともあるでしょう。繁忙期以外の時期は比較的融通が利きやすく、日程の指定や料金の値引きに対応してもらいやすくなります。
引越し費用について、詳しくはこちらの記事をご覧ください。
引越し見積もりの相場はいくら?費用の目安や安く抑えるコツを解説

ここで言うところの引越し費用は、引越し業者を利用した場合の費用です。初めて一人暮らしする方や単身赴任される方など荷物が少ない引越しなら、レンタカーを借りたり、宅配便を利用したりして引越すことも可能。引越しの初期費用を大きく引き下げられます。
引越しの初期費用をシミュレーション

ここでは実際に引越しに必要な初期費用を、単身者とファミリー世帯を例にシミュレーションしてみましょう。
単身者・家賃6万円の場合
単身者が家賃6万円の物件へ引越す場合の初期費用のシミュレーションは以下の通りです。
<条件>
・車、ピアノなどの運搬無し
・エアコンの付け外し無し
・引越し先は隣県(100km未満)
・引越し時期は非繁忙期
| 家賃基準 | 金額(円) | |
|---|---|---|
| 敷金 | 1ヵ月 | 60,000 |
| 礼金 | 1ヵ月 | 60,000 |
| 仲介手数料 | 1ヵ月 | 60,000 |
| 前払い賃料 | 1ヵ月 | 60,000 |
| 保証料 | 1ヵ月 | 60,000 |
| 火災保険料 | 15,000 | |
| 引越し費用 | 50,000 | |
| 合計 | 365,000 |
敷金・礼金がそれぞれ1ヵ月の物件へ引越しした場合の初期費用は上記の通りです。引越し時期は繁忙期を避けたため、割増料金は発生していません。また、エアコンの付け外しや自動車やピアノといった大物荷物の運搬はないため、特別作業に伴う追加料金もありません。
上記の引越しは少ない荷物を近隣に運んだ想定をしています。引越しの内容としては非常にシンプルですが、敷金・礼金が無料の物件を選ばなかったこともあり、初期費用は家賃の6倍程度の金額が必要という結果になりました。
ファミリー世帯・家賃12万円の場合
ファミリー世帯が家賃12万円の物件へ引越す場合の初期費用のシミュレーションは以下の通りとなりました。
<条件>
・ピアノの運搬が1台有り
・エアコンの付け外しが2台あり
・引越し先は隣県(100km未満)
・引越し時期は非繁忙期
| 単位 | 金額 | |
|---|---|---|
| 敷金 | 1ヵ月 | 120,000 |
| 礼金 | 1ヵ月 | 120,000 |
| 仲介手数料 | 1ヵ月 | 120,000 |
| 前払い賃料 | 1ヵ月 | 120,000 |
| 保証料 | 1ヵ月 | 120,000 |
| 火災保険料 | 20,000 | |
| 引越し費用 | 150,000 | |
| エアコンの付け外し | 2台 | 60,000 |
| ピアノ運搬 | 1台 | 50,000 |
| 合計 | 880,000 |
敷金・礼金がそれぞれ1ヵ月の物件へ引越しした場合の初期費用は上記の通りです。繁忙期を避けた引越しとなりましたが、単身者に比べて荷物の量が多いため、引越し料金が高額になっています。
また、引越し前の家で使用していたエアコンの付け外しやピアノの運搬が必要であるため、特別作業に伴う追加料金が発生しています。
ファミリーの引越しは荷物の量が多く、生活様式に合わせた家具・家電品を購入する機会が増えるため、単身者にはない費用が発生しやすい傾向があります。さらに家族の人数が多い家庭は荷物がトラック1台に収まりきらず、中型トラック2台か大型トラック1台が必要になることもあるでしょう。
ファミリー層は家族構成などの影響により、費用の変動が激しくなる傾向があります。初期費用の総額が家賃の7~8倍を超える場合も考えられるので、引越し予定が具体化する前から資金を準備する必要があるでしょう。
引越しの費用が払えない……クレカ払いは可能?

何らかの事情で急きょ引越しをしなければならなくなったときは、初期費用分の貯金を確保できないこともあるでしょう。できれば不足分をクレジットカードで後払いにしたいところですが、引越しの初期費用にクレジットカード払いは使えるのでしょうか。
近年、初期費用のクレジットカード払いに対応する管理会社が増加傾向にあります。物件によっては大家さんの意向でクレジットカード払いを認めていない場合もありますが、利用可の管理会社が使う物件では、主に以下の初期費用の支払いにカードを利用できます。
・敷金
・礼金
・前払い賃料
・仲介手数料
このほかにも、保証会社に支払う保証料、引越し業者に支払う引越し費用、保険会社に支払う火災保険料も、会社によってはクレジットカード払いに対応しています。
クレジットカード払いは分割やリボ払いによって支払いタイミングを調整できるため、手持ちの資金が足りなくても引越しできる可能性があります。ただし、分割払いやリボ払いを利用すると利息が発生するので、支払総額が引き上がる可能性がある点には注意が必要です。
高すぎる初期費用を抑える方法

引越しにかかる初期費用は、単身の引越しであっても多くの場合、数十万円におよびます。高すぎる初期費用に引越しを躊躇する人も多いと思われますが、初期費用を少しでも抑える方法はないのでしょうか。
敷金・礼金・仲介手数料が不要な物件を探す
初期費用の内訳で大きな割合を占める敷金・礼金・仲介手数料が不要の物件を選べば、初期費用を半額程度まで抑えられるかもしれません。物件広告に掲載された時点で敷金・礼金がゼロの物件だけでなく、交渉により設定されていた敷金・礼金をゼロにしてもらうこともできるでしょう。
敷金・礼金・仲介手数料のうち、交渉で値引きしてもらいやすいのが礼金です。礼金は大家さんへのお礼金という性質の費用です。ゼロにすることで大家さんの収入に直接的な影響がありますが、入居が決まれば数年間に渡って家賃収入が入るようになります。長期的には家賃収入でプラスに転じることが予想できるので、それで入居してもらえるなら値引きするという大家さんも存在します。
敷金も交渉によりゼロにできる可能性はありますが、退去時の原状回復費用を預けている性質があるため、必ずしもゼロとすることがメリットになるとは言い切れません。かえって退去時の原状回復費用の負担が厳しくなる場合もあるので、資金に余裕があるなら無理にゼロにしてもらう必要はないでしょう。
仲介手数料は、仲介を請け負う管理会社に支払う手数料です。近年は入居者側からの仲介手数料ゼロをうたう管理会社が増えています。請求された仲介手数料を無料にしてもらうのは困難ですが、最初から無料に設定されている管理会社で物件を探せば、他の管理会社よりも初期費用を低く抑えられるかもしれません。
閑散期に引っ越す
引越し業者の繁忙期は毎年2~4月です。裏を返せば、この時期を外せば引越し業者は手が空き気味になるので、引越し費用の値引きを持ちかけやすくなります。
特に交渉を成功させやすいのは、引越し業者の閑散期にあたる5月、7月、8月、11月付近です。引越し業者は少しでも仕事を獲得したい時期なので、通常料金よりも安く依頼できる可能性が高くなるでしょう。また、人員1人分の料金で2~3人が対応してくれる場合もあり、安全かつスピーディな引越し作業が期待できます。

引越しの初期費用を抑えるには「フリーレント」の物件を選ぶというのも効果的です。フリーレントとは、入居後、一定期間の家賃が無料になる契約を指します。たとえば、2ヵ月間家賃が無料の物件であれば、入居時に前払い賃料を支払う必要がありません。フリーレントの物件を選ぶことで数万円単位で初期費用を下げられます。
まとめ
引越しにかかる初期費用には総額が高額になる傾向があります。引越し先の家賃の5~6ヵ月分が相場といわれていますが、物件の条件や運び入れる荷物の内容によってはさらに引き上がる場合もあります。
初期費用のうち、大きな割合を占めるのが敷金・礼金・仲介手数料です。これらの費用は物件選びや交渉によって無料、もしくは割引が期待できるので、繁忙期を外した時期に管理会社に相談してみるとよいでしょう。
監修者プロフィール
 監修者
監修者
- 亀梨 奈美
- 株式会社real wave代表取締役。大手不動産会社退社後、不動産ライターとして独立。
2020年に株式会社real wave設立。不動産全国紙の記者として、不動産会社や専門家への取材多数。
「わかりにくい不動産を初心者にもわかりやすく」をモットーに執筆している。