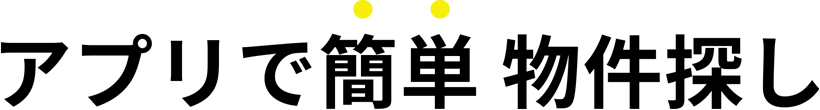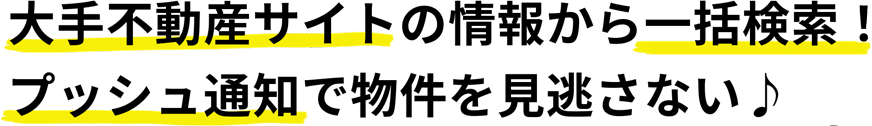住まいのコラム
隣人トラブル事例5選!
相談先・対処法・回避策を解説
最終更新日:
 監修者
監修者
- 亀梨 奈美
- 不動産ジャーナリスト/株式会社real wave代表取締役
- 隣人トラブルはどうすれば回避できる?
- 隣人トラブルの多くは、良好な人間関係とモラルの高さによって防止できます。しかし住民次第でトラブルを完全に防止することは難しいため、トラブルが起きた際には管理会社や地方自治体、警察などの窓口に解決方法を相談するとよいでしょう。どうしても解決が難しいようなら、別の物件への引越しも選択肢のひとつです。
賃貸住宅は多くの人が同じ建物に住む住居形態です。生活習慣やリズムが異なる人が集まれば、それだけ住民同士の摩擦も増えるもの。小さな価値観の違いが問題へと発展することも多く、いつ誰がトラブルに巻き込まれるかわかりません。
毎日の生活におけるストレスになりやすい隣人トラブルは、どのように対処すればよいのでしょうか。今回は集合住宅で発生しやすい隣人トラブルの事例と、トラブルの対処法・回避策についてご紹介します。
よくある隣人トラブル事例5選

隣人トラブルはどの集合住宅でも発生する可能性がありますが、トラブルの内容はいくつかの種類に集約されます。ここではよくある隣人トラブルとして、代表的な事例を5つ紹介します。
(1)騒音トラブル
隣人トラブルの代表格ともいえるのが騒音トラブルです。隣の部屋から聞こえる音楽のボリュームや上階からの足音など、音に関するトラブルは年代や家族構成を問わず発生します。
夜間の楽器演奏や大ボリュームのテレビ音声のようなわかりやすい騒音だけでなく、通常ボリュームの会話や足音といった生活音もトラブルの温床になります。
音に対する敏感さは個人差が大きいことから、知らない間に隣室の住民にストレスを与えているというパターンもあるでしょう。
(2)ゴミ出しをめぐるトラブル
一般的に、集合住宅の住民がゴミを出す場所はアパートやマンションごとにごみ収集ボックスが設けられています。もし住民の中にゴミの回収日を正しく把握していなかったり、分別を正しく行わなかったりする人がいると、いつまでもボックスの中にゴミが残りっぱなしになってしまうでしょう。
残されたゴミはいずれ悪臭を放つため、集合住宅の住民だけでなく近隣地域にも迷惑をかけることになりかねません。そうした問題が続くと住民間で犯人捜しが行われるなど、ギスギスした悪い雰囲気が生まれやすくなるでしょう。
(3)においによるトラブル
においに関するトラブルは、集合住宅で非常に頻発しやすい問題のひとつです。前述のゴミのにおいだけでなく、ペットの糞尿、下水から上がってくる悪臭などトラブルのもととなるにおいの種類はさまざまです。
また、近年では部屋にため込まれたゴミが悪臭を放ち、近隣の住民全体が健康被害を引き起こすといったゴミ屋敷問題も増えています。
(4)人間関係に伴うトラブル
集合住宅は人が集まる場所である以上、何かしらの人間関係が生まれやすくなります。お互いに心地よく生活できるように良好な人間関係を保ちたいものですが、全ての住民が好意的であるとは限らず、トラブルを招きやすい性格の人もいます。
住民同士の挨拶を無視するといった小さな不快感が引き金となり、騒音やゴミ出しルールへの注意が大きな揉めごとに発展することも考えられます。
(5)自治会のなかでのトラブル
大きなマンションでは、住民同士の集まりである自治会を組織している場合があります。自治会は住民間の交流だけでなく、マンションでの生活を快適にするための自治組織という側面があります。活動費は自治会員が分担して負担しますが、マンションによっては高額の自治会費を請求され、一部の役職者の飲食費に充てられるといったケースもあるようです。
また、自治会歴が長い住民が権力者となり、独自のルールで会を運営するという場合も少なくありません。新たに会員となった住民が自治会主体のお祭りで下働きを強要されるといったケースもあり、自治会に対する不満から住民同士のトラブルに発展することもあるでしょう。

ご近所付き合いが希薄になったことに加え、コロナ禍で在宅時間が伸びたことで、隣人トラブルは増加傾向にあります。どんな方であっても、隣人トラブルに遭遇してしまう可能性はあります。決して他人事とは思わず、想定されるトラブルや対処法を知っておくようにしましょう。
隣人トラブルの適切な対処法!どこに相談すればいいの?

隣人トラブルに巻き込まれてしまうと、その集合住宅での生活が快適ではなくなってしまいます。少しでも早く解決できるよう、隣人トラブルが発生した際の相談先はあらかじめ確認しておきましょう。
家主・管理会社
家主や管理会社は、最初に選びたい相談先です。管理者として住民が快適に生活できる環境を整備する義務があるので、相談内容に応じた早急な対応が期待できます。
相談する際には、ただ「隣の家がうるさい」といった内容ではなく、具体的な情報を提供するのが望ましいです。「いつ」「どこから」「誰が」「どのような行動をして」「どのような被害があるか」といった情報を提供できるよう、トラブルの記録はできるだけ細かく残しておきましょう。
役所
市役所や町役場でゴミや騒音、悪臭といったトラブルに関する相談を受け付けている自治体も見られます。原則として地域住民に広く影響があるトラブルへの対応が中心となりますが、個人的なトラブルの解決に繋がる専門家を紹介してくれる自治体もありますので、何らかの隣人トラブルに巻き込まれた際には一度相談してみるとよいでしょう。
警察
トラブルが不法行為にまで発展するような場合は、警察へ相談することも検討してみましょう。睡眠障害を引き起こすほどの騒音や、落書きやゴミ放置などの嫌がらせは軽犯罪法や刑法に抵触する可能性があります。
身の危険を感じた際には110番へ通報し、被害がひどい場合には被害届の提出も検討しましょう。

隣人トラブルに対処する際の鉄則は、直接、相手と対峙しないことです。どんなに迷惑を被っていたとしても、相手は隣人。直接、対峙することで関係性が悪化してしまうと、さらに住み心地が悪くなり、さらなるトラブルにも発展しかねません。
隣人トラブルを回避するための方法

隣人トラブルは対処法を知る以上に、発生させないことが第一の対策です。可能な限り隣人トラブルを回避するためも、次に紹介するような方法に取り組んでみるといいでしょう。
隣人と良好な関係を構築しておく
隣人とのトラブルを防止する予防策のひとつが、良好な人間関係の構築です。近隣住民に仲がいい人が多いほど、少々の問題があってもトラブルにまで発展しにくくなります。
もしゴミ捨てのルールを守らない住民がいたとしても、日頃から仲良くしておけばそれとなく注意もしやすくなります。また注意を受ける側も、知り合いには迷惑をかけたくないという気持ちが芽生えることで、ルールを守った生活を送るようになるかもしれません。
ルールやモラルを守って生活する
隣人トラブルは常に自分が迷惑をかけられる側にいるとは限りません。気がつかないうちに加害者側に回ってしまい、クレームを受ける側になることもありえます。
自分が隣人トラブルの発端にならないためには、集合住宅で生活する上でのルールやモラルをしっかりと守ることが大切です。ゴミ捨ての指定日を守るのはもちろん、夜遅くに大きな音を立てない、玄関先を常に清潔に保つなど、小さなルールをひとつひとつ守るように心がけましょう。
引越しも選択肢のひとつ
隣人トラブルは努力によってある程度予防・回避できますが、近所に悪意ある住民が住んでいるような場合は、どうしても避けきれないこともあります。
そういった住民の行動を改善させるのは困難です。自分ができる範囲の対策をしても状況が変わらないようなら、よりよい環境のマンション・アパートへ引越し、隣人を含めた環境を変えるのもよいでしょう。
隣人トラブルを避けるために物件選びの段階で確認しておきたいポイント

隣人トラブルを避けるには、入居の時点でトラブルが起きにくい物件に住むのが理想的です。入居前に確認できる隣人トラブルの回避ポイントをご紹介します。
物件の遮音性
隣人トラブルの代表ともいえる騒音トラブルは、物件の構造によって発生頻度が大きく異なります。建物の遮音性は、一般的に以下の順番で高いといわれています。
鉄筋コンクリート造(RC造)>鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造)>重量鉄骨造>軽量鉄骨造>木造
騒音トラブルが起きにくい住まいを選ぶなら、鉄筋コンクリート造や鉄骨鉄筋コンクリート造のマンション・アパートを選ぶのがおすすめです。ただし、上記の順番は一般論であり、建物によっては別の対策で遮音性を高めている場合があります。遮音対策の詳しい内容が気になるようなら、対象の物件の仲介会社や管理会社に問い合わせておくとよいでしょう。
共用部分の管理・清掃状況
隣人トラブルの解決には、家主や管理会社の力を借りることになります。物件の管理に力を入れている家主や管理会社ほど積極的な問題解決が期待できますが、その積極性を図るひとつの基準が共用部分の清掃状況です。
住民が過ごしやすいように共用部分を清潔に保っている物件は、家主や管理会社の積極的な管理姿勢がうかがえます。また、ゴミステーションを含む共用部が管理されているだけで防げるトラブルもありますので、きれいな物件ほど穏やかな生活環境が期待できるでしょう。
反対にいつまでも古い掲示物が共用部の掲示板に残っているような物件は、家主や管理会社の助力があまり期待できないかもしれません。
過去に起きたトラブル事例
可能であれば、仲介会社や管理会社に過去に発生したトラブルの事例を教えてもらうのがおすすめです。トラブルの内容や解決までの期間、解決に至った経緯を知ることによって、入居後に注意すべきポイントが判断しやすくなるでしょう。
なお、現在進行形で隣人トラブルが発生している物件は、今後短期間で解決する保証は一切ありません。その物件に住むことで自分も巻き込まれることも考えられるので、できるだけ避けたほうが無難です。
まとめ
賃貸住宅では、大なり小なり隣人トラブルは発生します。しかし遮音性が高い物件では騒音トラブルが起きにくいなど、物件によって発生するトラブルの内容や頻度は異なります。
また、隣人トラブルの多くは住民同士の人間関係の濃密さやモラルの高さによって防止できます。自分自身がトラブルの加害者側に回ることのないよう、近隣住民との関係は良好に保ちながらモラルを持った生活を送るように心がけましょう。
監修者プロフィール
 監修者
監修者
- 亀梨 奈美
- 株式会社real wave代表取締役。大手不動産会社退社後、不動産ライターとして独立。
2020年に株式会社real wave設立。不動産全国紙の記者として、不動産会社や専門家への取材多数。
「わかりにくい不動産を初心者にもわかりやすく」をモットーに執筆している。