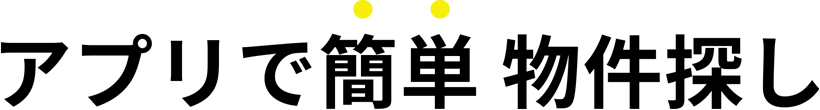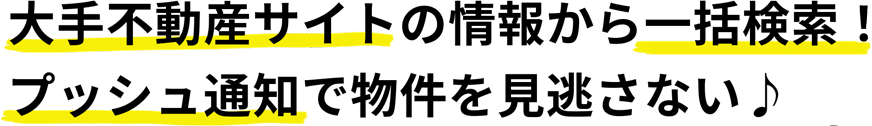住まいのコラム
アパートの騒音に対する正しい対処法!
相談先は警察?管理会社?
最終更新日:
 監修者
監修者
- 亀梨 奈美
- 不動産ジャーナリスト/株式会社real wave代表取締役
- 騒音トラブルが起きたらどう対処すればいい?
- 近隣の騒音を迷惑と感じるようになったなら、まずは家主や管理会社に詳細な情報を添えて相談しましょう。もし嫌がらせなどの直接的な被害に発展してしまったなら、早めに警察へ相談する必要があります。絶対に直接苦情は入れないようにし、必ず第三者を交えた解決を図りましょう。
賃貸生活において遭遇しやすい騒音トラブル。住民同士の生活リズムやスタイル、価値観の違いから発生するため、発生を予測しにくく、解決にも時間がかかります。
近隣住民が出す騒音に悩まされている場合、どのような対処をするとよいのでしょうか。今回は騒音トラブルが発生したときの対処法についてご紹介します。
目次
アパートの騒音トラブルが起こる主な要因

騒音が住民同士のいさかいに発展する騒音トラブルはなぜ起きてしまうのでしょうか。
騒音トラブルの多くは、隣や上下の部屋から聞こえる音をうるさいと感じることから始まります。静かに過ごしたいと思っている時に聞こえるオーディオやテレビなどの音は、自分の室内とは異なる聞こえ方になることも影響し、わずらわしさを感じやすくなります。
また、冷蔵庫やエアコン、電子レンジなどの電化製品の音も騒音トラブルの原因です。最近の電化製品は静音性に優れた製品が増えていますが、古い電化製品が壁が薄い部屋で使われていると、隣家に稼働音が聞こえ続けることにもなりかねません。
人やペットから出る音も騒音トラブルが起きる原因のひとつです。日中の話し声程度ならあまり問題にはなりませんが、周辺が静かな深夜帯の話し声は響きやすいため、隣室や上下の部屋にまで届きやすくなります。さらには、断続的に発生する子どもの足音やペットの鳴き声が原因で大きなトラブルになることも珍しくありません。
騒音トラブルは、意図的に大きな音を響かせるような住民だけが原因になるわけではありません。普段のなにげない生活の中から出る音がトラブルの種になりますので、誰もが自分が出す音に注意する必要があります。

一つ屋根の下に複数の世帯が暮らす集合住宅では「お互い様」の精神が求められます。近代社会において音が一切ない生活を送ることはできないことから、「騒音」とみなされるかどうかは相手が許容できる範囲であるかどうか次第ともいえます。度を超えた騒音は対処しなければなりませんが、集合住宅に住む以上、一定の協調性は必要だといえるでしょう。
ストレスを感じる騒音の音量はどのくらいか
音のうるささが原因となり引き起こされる騒音トラブルですが、具体的にどの程度の音が騒音と感じられるのでしょうか。
環境庁は「騒音に係る環境基準」として以下の基準を定めています。
| 類型 | 基準値 | |
|---|---|---|
| 昼間 | 夜間 | |
| AA | 50デシベル以下 | 40デシベル以下 |
| A及びB | 55デシベル以下 | 45デシベル以下 |
| C | 60デシベル以下 | 50デシベル以下 |
出典:環境庁
注)
1 時間の区分は、昼間を午前6時から午後10時までの間とし、夜間を午後10時から翌日の午前6時までの間とする。
2 AAを当てはめる地域は、療養施設、社会福祉施設等が集合して設置される地域など特に静穏を要する地域とする。
3 Aを当てはめる地域は、専ら住居の用に供される地域とする。
4 Bを当てはめる地域は、主として住居の用に供される地域とする。
5 Cを当てはめる地域は、相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される地域とする。
上記の例から、時間帯や場所によって基準は異なりますが、40~60デシベルを超えると騒音になりやすいと考えられます。
40~70デシベル前後に該当する物音の例は以下の通りです。
| 音の大きさ | 物音の例 |
|---|---|
| 30デシベル | ホテルの室内 |
| 40デシベル | 昼間の戸建住宅、図書館の館内 |
| 50デシベル | 昼間の高層住宅地域、書店の店内 |
| 60デシベル | 銀行の窓口周辺、博物館の館内 |
| 70デシベル | 地下鉄の車内、昼間の主要幹線道路周辺 |
出典:環境省「生活騒音」
この例からみると、普段の生活を送る上で発生する音は、一般的な住宅においては騒音になりにくいことがうかがえます。
しかし、薄い壁や音が響きやすい構造など、物件そのものが騒音トラブルになりやすい要因を持っている場合があります。また、昼間と同じ感覚で洗濯機や掃除機を使ったためにトラブルになったという例も少なくありません。
さらには、隣の住民が特に音に対して神経質な人であるため、基準値内の音を騒音として通報されることもありえます。
自分が騒音元にならないためには、できるだけ音を出さないような配慮を徹底するような心づもりが適切であるといえるでしょう。
アパートの騒音に対する基本的な対処法

アパートにおける騒音は、住民本人がどれだけ注意していても避けられるものではありません。近隣の部屋から出る騒音により生活に支障が出ているような場合、どのような対処ができるのでしょうか。
騒音に悩んだらまずは家主や管理会社に相談を
騒音に悩み始めたら、まずは家主や管理会社への相談するのがおすすめです。家主や管理会社といった物件の管理人は住民に快適な生活を提供する義務があるため、何らかの対応が行われると期待できます。
ただし、家主や管理会社は共用部の掲示板への注意文掲示や全体への手紙の投函などから対応を始めるため、解決まで時間がかかる場合があります。
相談してもすぐに騒音が止まるとは限りませんので、被害が小さいうちから相談を始めておき、経過を報告できるような関係を作っておくとよいでしょう。
家主や管理会社に相談するときのポイント
家主や管理会社に相談する際には、できるだけ詳細な情報を提供が重要になってきます。「近所のどこかがうるさい」という程度の情報では、家主や管理会社は具体的なアクションを起こしにくいため、以下のような情報を添えて相談するのが望ましいでしょう。
・いつ頃から騒音を感じるようになったか(具体的な日付、何日くらい前からなど)
・どのような音が聞こえるのか(洗濯機や掃除機の音、音楽、話し声など)
・何時頃に聞こえるのか(夜21時過ぎ、深夜2時過ぎなど)
・どの程度の頻度・長さで聞こえるのか(週に3~4回、3時間程度連続するなど)
・音が聞こえる部屋の方向
情報は詳細であることが望ましいですが、相談時点ではっきりとした情報を集めていない場合は、まずはわかる範囲でできるだけ情報を集めましょう。その後は騒音の発生時間や内容を記録し、2度目以降の相談時に伝達するのがベターです。
「直接」苦言を呈するのはNG
もし騒音元が判明したとしても、直接騒音に対する苦情を伝えるのは避けるべきです。たとえ苦情を入れられても仕方ないほどの騒音を出しているとしても、直接クレームを入れられると攻撃を受けたと感じてしまい、別の問題を引き起こしてしまうおそれがあります。
生活音にクレームを入れられたことをきっかけに、意図的に音楽を大音量で流すようになるなど、被害を拡大させてしまうことも。さらにはクレームを入れた側に対する個人的な嫌がらせに発展してしまうかもしれません。
また、騒音が隣からだと感じられていても、建物の構造のせいで斜め上の部屋の音が隣から聞こえてくるようなケースもあります。濡れ衣を着せられた隣の人が気分を害した結果、険悪な関係になってしまうことも考えられます。
冷静で穏やかに問題を解決するためにも、第三者に入ってもらうようにしましょう。
警察への通報を考えるべき騒音トラブルは?

騒音トラブルはただうるさいというだけでなく、被害によっては軽犯罪法違反や傷害罪を問われる場合もあります。家主や管理会社へ相談しても解決が望めないほどのトラブルに見舞われた場合には、警察への相談も視野にいれましょう。
以下で、警察への通報も視野に入れるべき騒音トラブル例を挙げます。
真夜中・早朝の大音量の騒音
真夜中や早朝に流される大音量の騒音は、近隣住民の睡眠不足を引き起こす原因となります。夜中に行われるパーティや大音量の音楽が連日続くようなら、警察への相談を検討してもよいでしょう。
地域によっては条例によって時間帯ごとの音量を規制しているため、注意や拘留の対象となる場合があります。また軽犯罪法では公務員に注意された行為を繰り返すことを違反対象としているので、警察から何度も注意をしてもらうことで、法律違反者として取り締まってもらうことも期待できるでしょう。
騒音を指摘されたことによる嫌がらせ
騒音を直接指摘すること、騒音元からの嫌がらせを受けてしまうケースもあります。遅い時間帯の音量をさらに上げられる、設備・施設への攻撃や対面中の罵倒など、さまざまな形で嫌がらせを受ける恐れがあります。
騒音トラブルの範疇に収まらないような嫌がらせは、器物損壊罪や侮辱罪、暴行罪などが適用される場合もあるので、身の危険を感じるようならすぐに警察へ通報しましょう。
相談専用ダイヤルの活用も検討する
騒音で迷惑を被ってはいるけれど、110番するほどの被害ではなさそう……と感じるようなら、まずは警察相談ダイヤルへの連絡するのがおすすめです。
「#9110」は、犯罪や事故に該当しないようなトラブルを相談できる警察の窓口で、相談内容によって適切な窓口へと誘導してくれます。一人ではできないような解決方法の提案や今後の対策の提示が期待できます。
また、#9110への相談が警察への相談実績になりますので、今後トラブルが発展してしまった場合もスムーズに対応してもらえるでしょう。
騒音トラブルを回避したい!物件選びで見ておくべきポイント

新たに引越した先では、できるだけ騒音トラブルは回避したいものです。騒音による影響は、建物の構造や部屋の位置を考えることで減らすことができます。静かで快適な生活を手に入れるためにも、次に紹介するようなポイントを意識して部屋を選ぶとよいでしょう。
構造
騒音トラブルを避ける効果的な方法のひとつが、音が響きにくい建物に住むことです。建物の建築方法はいくつかの種類があり、一般的に次の順番で防音性が高いといわれています。
1.鉄筋コンクリート造(RC造)
2.鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造)
3.重量鉄骨造
4.軽量鉄骨造
5.木造
木造は通気性が高く湿気がこもりにくいというメリットがありますが、防音性はあまり高くありません。反対に鉄筋コンクリート造は機密性が高く防音性にも優れていますが、比較的新しい物件が多く家賃が高い傾向があります。
出せる家賃の予算と相談し、できるだけ防音性が高い構造の物件を選ぶようにすれば、騒音問題に悩まされるリスクを下げられるでしょう。
部屋の位置
騒音は隣室だけでなく、上下階からも発生する場合があります。騒音のリスクをできる限り下げたいなら、物件選びの条件に隣接している部屋が少なさを加えてみましょう。
最上階の部屋は、トラブルになりやすい上階からの足音の心配がありません。また、角部屋は隣室が一方だけにしかないため、隣からの騒音に悩まされるリスクを半分に減らせるでしょう。
ただし、騒音トラブルは生活音が原因になることも多いため、油断すると自分が騒音の発信元になってしまいます。特に下に部屋がある場合には、自分や家族の足音が問題になることも十分に考えられます。
自分が被害を受ける場合の対策だけでなく、自室から騒音を出さないような対策も注意が必要です。
入居者のマナー・モラル
新居選びの前には、すでに入居している住民のマナー・モラルも確認しておくのが望ましいでしょう。全員が優れたモラルを持っているかどうかを調べるのは難しいですが、共用部の状態を調べることで、大まかな住民の傾向を確認できます。
廊下やロビーにゴミがなく、清潔な状態が保たれている物件からは、住民がきれいに使おうとする意思がうかがえます。チラシの処分が求められるポスト前や、ゴミ出しルールへの意識が現れるダストボックスは特に注意して確認しておきたいポイント。また共用部の掲示板に古い掲示物がなく、廊下やロビーの照明が切れっぱなしになっていないようなら、家主や管理会社の管理が行き届いていると予想できます。
共用部には住民のモラルや管理人の意識が現れやすいため、内見の際には忘れずにチェックしておきましょう。

一度、内見しただけでは、隣人の生活音や外から聞こえてくる音の程度を把握することはできません。できれば曜日や時間帯を変えて複数回内見し、内見時には周辺を歩いてみることもおすすめします。
まとめ
騒音トラブルに遭遇してしまうと、そのアパートでの生活がしにくくなってしまいます。近所からの騒音が迷惑に感じられるようなら、まずは家主や管理会社へ相談しましょう。被害がひどいようなら警察への相談も視野に入れた行動が必要です。
できるだけ騒音の被害を受けないようにするためには、鉄筋コンクリート造の物件や角部屋・最上階といった騒音トラブル自体が発生しにくい部屋を選ぶとよいでしょう。
騒音トラブルはどの物件でも遭遇するリスクがあります。被害に遭わないためにも物件選びの知識を身につけつつ、騒音が発生した際には第三者を交えたトラブル解決に臨みましょう。
監修者プロフィール
 監修者
監修者
- 亀梨 奈美
- 株式会社real wave代表取締役。大手不動産会社退社後、不動産ライターとして独立。
2020年に株式会社real wave設立。不動産全国紙の記者として、不動産会社や専門家への取材多数。
「わかりにくい不動産を初心者にもわかりやすく」をモットーに執筆している。