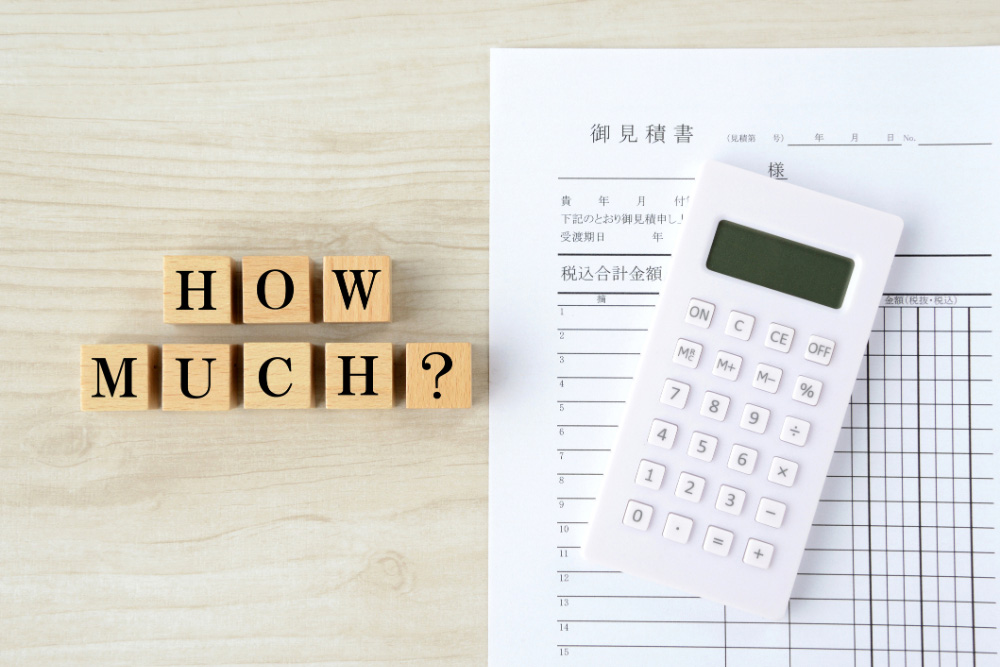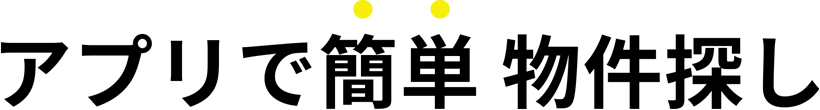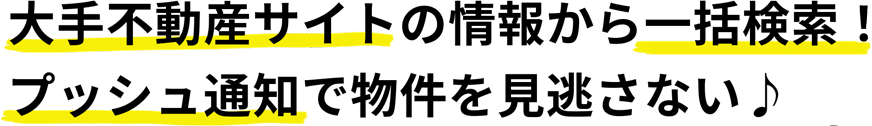住まいのコラム
木造アパートのメリット・デメリット!
音漏れや耐震性は大丈夫?
最終更新日:
 監修者
監修者
- 矢野 翔一
- 2級ファイナンシャルプランニング技能士(AFP)、宅地建物取引士、管理業務主任者/有限会社アローフィールド代表取締役社長
- 木造アパートのメリット・デメリットは?
- 木造アパートは築古の物件が多いこともあり、人気の鉄骨造・RC造に比べて安い家賃で入居できる物件が多めです。通気性が良く湿気に強いため、夏場のジメジメとした不快感が軽減されます。一方、耐震性や防音性にはあまり期待できません。また、通気性が良い分エアコンの効果も低下する傾向があります。
建物の構造には「木造」「鉄骨造」「RC(鉄筋コンクリート)造」などの種類があり、それぞれ使われる工法や材料が異なります。古くからあるアパートの多くは木造であり、家賃の手頃さや建物の豊富さから、初めての一人暮らしに向いているといわれています。
一方、近年の主流である鉄骨造やRC造に比べると不便な点があるのも事実です。木造アパートはどのような選ぶべきメリットがあり、避けたいデメリットがあるのでしょうか。今回は木造アパートのメリット・デメリットをさまざまな観点から解説します。
木造アパートの耐用年数と耐震性

木造アパートの問題点として指摘されるのが「耐用年数」と「耐震性」です。築40~50年を経過した古い物件も多い木造アパートの安全性は、どのように評価されているのでしょうか。
法定耐用年数は22年
木造アパートの法定耐用年数は「22年」と決められています。
法定耐用年数とは、財務省令によって定められた固定資産を使用できる年数です。会計処理において資産の取得にかかった費用の償却期間として用いられており、木造アパートなら建築から22年経過すると、会計上では資産価値がなくなるとされています。
なお、法定耐用年数は会計上において資産価値が存在する期間であり、資産を使える物理的な耐用期間とは一致していません。実際に木造アパートの多くは22年を超えて使用され続けており、中には50年以上に渡り使われ続けている建物も。そのことから耐久性に優れた構造だといえるでしょう。
耐震性は築年帯によって異なる
鉄骨造やRC造に比べ、木造アパートは耐震性に劣るといわれています。しかし地震大国である日本では、古くから地震に対する備えには力を入れており、耐震基準を設けて木造建築の建物の耐震性を高めてきました。
日本の耐震基準は過去に数度の見直しが行われており、現存する建物には建築された年代に応じて3種類の耐震基準が適用されています。
旧耐震基準
1981年(昭和56年)5月31日以前にまでに建築確認が出された建物に適用されている耐震基準が「旧耐震基準」です。2023年現在「おおむね築41年以上」の物件が旧耐震基準にあたります。「おおむね」というのは、建築確認が出されてから実際に建物が建つまで一定の期間がかかるため、築年数だけで耐震基準は判断できないからです。
旧耐震基準が適用された建物は、震度5強程度の揺れが起きても建物が倒壊せず、破損が起きても補修により生活可能な状態まで回復できる構造であるとされています。
新耐震基準
1981年(昭和56年)6月1日以降に建築確認が出された建物に適用された耐震基準が「新耐震基準」です。2023年現在、おおむね築24年〜築41年の物件が新耐震基準に該当します。
旧耐震基準を超える震度6強~7程度の揺れにも耐える構造基準として設定されており、一定規模を超える大きさの建物には、旧耐震基準に加え靱性(粘り強さ)を確保することが求められました。
2000年基準
2000年基準は、1995年に発生した阪神淡路大震災で木造住宅が数多く倒壊したことを受けて見直された最新の耐震基準です。2000年(平成12)年6月以降に建築確認申請が出された木造の建物が該当します。2023年現在、新築〜おおむね築23年のアパートは2000年基準で建築されています。
新耐震基準の要求をさらに厳格化したのが特徴であり、新耐震基準よりも優れた家のバランスの良さが追求されています。具体的には基礎設計のための地盤調査の実施、接合部等への金物の使用、バランスの良い耐震壁の配置といった規定が盛り込まれ、安全性とバランスが強化されました。
この改正により、従来は設計者任せとなっていた耐震性に法的な基準が設けられ、より均質かつ高度な耐久性が実現しています。

旧耐震基準に該当する木造アパートがすべて危険というわけではありません。耐震診断を実施していて現行の耐震性を有していると判断された木造アパートであれば安心です。気になる方は耐震診断の実施の有無を確認してみましょう。
木造アパートのメリット

近年は鉄骨造やRC造の集合住宅に人気が集中していますが、木造アパートには木造アパートの良さがあります。ほかの構造にはない木造アパートならではのメリットとはどのようなものでしょうか。
賃料が安い
一般的に、木造アパートは鉄骨造やRC造のアパート・マンションに比べ、家賃が安めに設定されています。木造建築は歴史が古く、木造アパートの中にも築年数が古い建物が多く含まれています。築年数が古い物件はすでに法定耐用年数を超えており、すでに建築費用の回収が終わっていることも珍しくありません。借金がなくあとは稼ぐだけという状態になっているため、低い家賃設定が可能となっています。
なお、安い家賃の物件は毎月の支払いを抑えられるだけでなく、初期費用や更新料も安くなります。初期費用の項目である敷金・礼金・仲介手数料や、契約更新時に支払う更新料は、「家賃○ヵ月分」と請求されます。ほかの物件も○ヵ月分の部分は大きく変わりませんが、家賃が安いほど基準が下がるため、支払う費用の差は大きくなるでしょう。
通気性が良い
木造建築のメリットの1つが通気性の良さです。湿気がこもりにくく湿度が調整しやすいため、暑い夏場の室内がジメジメとした空気になりにくくなります。
また木材には湿気を吸い取る性質があります。特に湿気の多い梅雨の時期には多くの湿気を吸収し、カビの発生を防いでくれるでしょう。
梁・柱が細くデッドスペースが少ない
鉄骨造やRC造では柱や梁に太い鉄骨を用いる必要があるため、壁や天井に張り出しを作らざるを得なくなります。なるべく目立たないような構造になるようには設計されていますが、部屋の四隅の一角だけ柱が張り出すような構造になってしまうと、自由なレイアウトを楽しめなくなるかもしれません。
木造アパートに使われる柱や梁は、鉄骨造やRC造に比べると細いため、余計な張り出しを作る必要がなくなります。部屋の隅にも家具を置きやすく、部屋を自由に広く使いやすくなるでしょう。

木は木材として加工された後も空気中の水分を吸収・放出します。そのため、夏の湿度が高い状況では空気中の水分を吸収し、冬の湿度が低い状況では木材に含まれている水分を放出することで湿度を最適な状態に保ってくれる性質があります。
木造アパートのデメリット!気になる音漏れは大丈夫?

木造ならではのメリットがある木造アパートですが、一方で「木造は避けるべき」という根強い意見も残っています。ほかの構造にはない木造が抱えるデメリットには、どのようなものがあるのでしょうか。
防音性が低い
木造アパートにおいて最も注意すべきポイントが防音性の低さです。木材は鉄骨やコンクリートに比べると軽いため、足音などの影響を受けやすくなります。またほかの構造よりも壁が薄く、材質も音を通しやすいため、隣の部屋の話し声や生活音が聞こえるという物件も珍しくありません。
気密性が低い
木造アパートは通気性が良いというメリットを紹介しましたが、裏を返せば気密性が低いと言い換えることができます。木造住宅の構造は、室内の空気が外に出る隙間ができることを避けられません。
そのためいくら冷房や暖房で温度を調整しても空気が逃げてしまい、冷房や暖房にかかる電気代が高くなってしまうことも考えられます。
火災のリスクが高い
木造アパートに使われる木材は燃えやすい材質です。近年では燃えにくい木造住宅に力を入れるメーカーが増えていますが、鉄骨造やRC造に比べるとやはり火災の被害に遭いやすい建物といえるでしょう。特に築年数が古い木造アパートほど燃えやすいため、火災への備えには常に注意を払う必要があります。
また、火災が起きやすい建物は、ほかの構造と比較して火災保険の保険料が上がる傾向が。ランニングコストもしっかり確認しておきましょう。
木造アパートのデメリットを解消するポイント

木造住宅には、構造上避けられないデメリットが複数存在しています。トラブルを避けながら安い家賃の物件に住み続けられるよう、デメリットを解消するためのポイントを知っておきましょう。
築浅物件を選ぶ
木造住宅はできるだけ築浅の物件を選ぶのがおすすめです。2000年以降に建築された木造住宅は最新の耐震基準をクリアしており、大規模な地震が発生しても家が大きなダメージを受ける心配はありません。
また、近年の木造住宅は耐火性能が大幅に向上しています。火事の心配が軽減できるのに加え、火災保険料も抑えられます。
築浅となると比較的家賃は高めになってしまいますが、木造住宅が抱える長期的な不安の多くを解消できるため、前向きに検討する価値はあるでしょう。
効果的な防音対策
木造アパートでトラブルになりやすい音の問題を解決するには、防音性を高める対策が効果的です。
代表的な足音対策に挙げられるのが柔らかい素材の防音マット。特によく動くお子さんがいるご家庭では、厚みがあり衝撃吸収性が高いジョイントマットを敷き詰めるのがおすすめです。足音に注意できる大人のみ住んでいるならば、厚みのあるカーペットやスリッパを使うだけでも十分な対策になるでしょう。
話し声やテレビの音が響くようなら、壁に貼り付ける防音シートの利用がおすすめ。音が隣室に向かなくなるよう、テレビの位置を変えるのも効果が期待できます。
なお、近年では木造住宅の壁に防音性が高い素材が用いられることが増えています。この点でも、やはり築浅物件を選ぶことそのものが効果的な対策になってくれるでしょう。
内見時には共用部分もチェック
アパート選び中の内見時には、部屋の中だけでなく共用部も忘れずにチェックしましょう。エントランスにチラシが落ちていたり、ごみ収集ボックスの周りが汚れていたりする物件は、小まめに対応してくれる管理人がいない可能性があります。管理人不在の物件は、トラブルを相談した際の反応が悪かったり遅かったりする可能性も。騒音問題の解決や火災事故の防止といった対応に高い期待ができないかもしれません。
安心して快適な生活を送れるアパートに入居するためにも、管理状態の判断材料となる共用部のチェックは忘れないようにしましょう。
まとめ
木造アパートは、国内に数多く存在する賃貸物件です。近年では鉄骨造やRC造が人気を集めていますが、家賃の安さや通気性の良さなど、木造ならではのメリットを評価する根強いファンも多く存在しています。
防音性や耐火性といった課題はありますが、十分な対策を行いながら物件を選べば、鉄骨造やRC造に負けない快適な住み心地を得られるでしょう。物件選びの選択肢を広げるためにも、良質な木造アパートも検討してみるのはいかがでしょうか。
監修者プロフィール
 監修者
監修者
- 矢野 翔一
- 関西学院大学法学部法律学科卒業。有限会社アローフィールド代表取締役社長。保有資格:2級ファイナンシャルプランニング技能士(AFP)、宅地建物取引士、管理業務主任者。
不動産賃貸業、学習塾経営に携わりながら自身の経験・知識を活かし金融関係、不動産全般(不動産売買・不動産投資)などの記事執筆や監修に携わる。