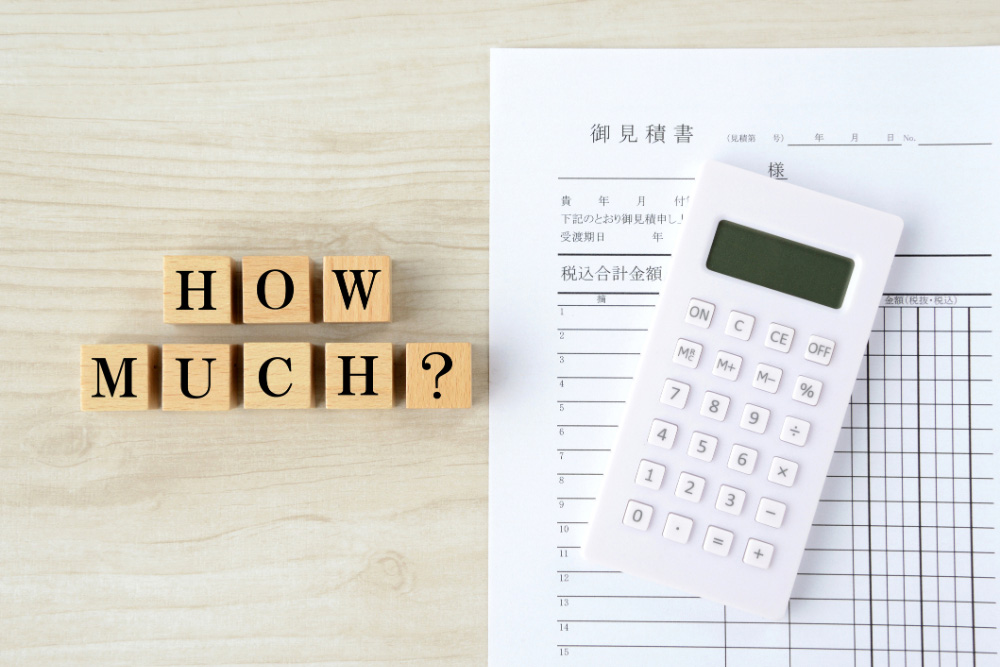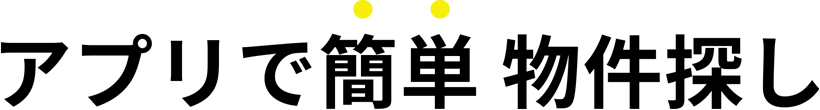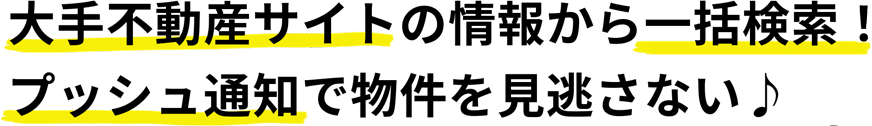住まいのコラム
給料に対する適切な家賃は?
一人暮らし・二人暮らしの目安を解説!
最終更新日:
 監修者
監修者
- 矢野 翔一
- 2級ファイナンシャルプランニング技能士(AFP)、宅地建物取引士、管理業務主任者/有限会社アローフィールド代表取締役社長
- 給料に対する家賃の適切な割合は?
- 総務省統計局の調査によれば、民営借家世帯における家賃の平均割合は総支出の26.4%と、1/4程度のようです。家賃の適正割合は手取り収入の1/3といわれることもありますが、近年では物価上昇の影響を受けて昔よりも支出が増えているため、1/4程度に収めるとよいでしょう。
「広い家に住みたい」「おしゃれなタワマンに憧れる」「駅近は譲れない」……など、住居にこだわる人は少なくありません。
しかし、住みやすい場所を追求すると、家賃はどこまでも上がってしまうものです。給料に対して家賃が高過ぎてしまうと、生活が圧迫されてしまい快適な生活を送るのは難しくなるでしょう。
給料に対し適切な家賃の額は、どの程度の金額なのでしょうか。今回は、給料の額を基準とした適切な家賃の決め方についてご紹介します。
給料に対する家賃の適切な割合

毎月支払いが発生する家賃。無計画に予算を決めると、家計を圧迫しかねません。そのため、自分の給料からどのくらいを家賃に充てるのが適切か、しっかり計算する必要があります。では具体的に給料のうちどの程度を家賃の目安にすればよいのでしょうか。
「手取り額の1/3が適切」は本当か
収入に対する家賃の目安として、一般的に手取り額の1/3以内に収めるとよいといわれています。しかし家賃の相場は地域によって異なり、また年収によって家賃にかけられる金額も変わるため、一概に1/3まで出してもよいとはいえません。
たとえば、手取り15万円の人が収入の1/3である5万円を家賃に使った場合、残りは10万円となります。ここから食費や水道光熱費、通信費などの支払いを済ませると、手元にはほとんど残らないでしょう。
一方で手取り45万円の人が15万円の物件に住む場合はどうでしょうか。家賃を支払った後でも手元に30万円が残るため、単身の人ならかなり余裕のある生活を送れるでしょう。家具家電のグレードを上げる、海外旅行に行くといった使い方に興味が無いようなら、住居をタワーマンションの高層階にするなど、家賃の割合を上げるといった選択肢も考えられます。
では、実際に現代の賃貸物件の利用者は、手取りのうちどの程度を家賃に充てているのでしょうか。
現代は手取り額の「1/4」が一般的
総務省統計局の「家計調査(家計収支編)調査結果」 によれば、2022年における全民営借家世帯において、住居費に費やした収入の割合は26.45%。およそ1/4程度という結果となりました。全年収帯の平均であるため、特定の地域や年収帯の傾向が反映された結果ではありませんが、家賃に使えるおおよその割合として参考になるでしょう。
かつては、「給料の額面金額のうち1/3を家賃に回してもよい」という時代がありました。しかし、近年は物価の上昇や各種税率のアップ、社会保障費負担の増加など、以前と同じ給与でも手取りが減り、支出が増える傾向にあります。そのため適正家賃の基準は額面から手取りとなり、また1/3では多いといわれるようになっています。
今後も続くであろう物価の上昇や税率のアップに備えるためにも、家賃の比率は手取りの1/4程度を目指すのがおすすめです。

25年ぶりの円安水準で、輸入品の値上がりによる物価高が進行しています。インフレによる物価高は、所得の上昇を伴うので問題ありません。しかし、所得が上がらない状況での物価高なので、家賃を抑えて物価高を乗り切るといった工夫が求められるでしょう。
手取りごとに見る家賃の適切な割合

家賃の割合は1/4が目安とご紹介しましたが、地域により家賃相場も変わってきます。1/4で収めるのが難しい場合もあるでしょう。ここでは、手取り額別に具体的な金額を一覧でまとめています。
おすすめの比率である1/4(25%)を中心に、その前後の金額も検討しましょう。
| 手取り額(月収) | 20% | 25% | 30% |
|---|---|---|---|
| 15万円 | 3万円 | 3万7500円 | 4万5000円 |
| 20万円 | 4万円 | 5万円 | 6万円 |
| 25万円 | 5万円 | 6万2500円 | 7万5000円 |
| 30万円 | 6万円 | 7万5000円 | 9万円 |
| 35万円 | 7万円 | 8万7500円 | 10万5000円 |
| 40万円 | 8万円 | 10万円 | 12万円 |
一人暮らし・二人暮らしの家賃の適切な割合

一人暮らしか二人暮らしかによっても、適切な家賃の割合は変わってくるでしょう。
ここで、総務省統計局が公表する「家計調査(家計収支編)調査結果」における、2022年に民営借家へ居住している一人暮らし・二人暮らしの生活費の割合をご紹介します。
| 項目 | 一人暮らし | 二人暮らし |
|---|---|---|
| 食料 | 20.638% | 23.545% |
| 住居 | 30.541% | 22.21% |
| 光熱・水道 | 6.567% | 7.64% |
| 家具・家事用品 | 2.517% | 3.231% |
| 被服及び履物 | 3.208% | 2.774% |
| 保健医療 | 3.741% | 4.091% |
| 交通・通信 | 10.65% | 13.175% |
| 教育 | 0% | 2.661% |
| 教養娯楽 | 10.126% | 6.628% |
| その他の消費支出 | 12.012% | 14.046% |
出典:総務省統計局「家計調査(家計収支編)調査結果 (2022年)」をもとに作成
上記のデータからは、一人暮らしでは収入の約30%が家賃に充てられていることがわかります。
ただ、前述したとおり、今後の物価上昇や税率アップを考慮すると、25%を目安とするのが安心といえるでしょう。
一方で、手取りが15万円~20万円前後では、地域によっては25%以内に収まる家賃の物件を借りられないおそれがあります。東京23区内のようにワンルームでも7万円を超えるようなエリアは狙わず、相場の低いエリアに家を借りるといった対策が必要です。
二人暮らしで双方に収入がある場合は、一人暮らしに比べて金銭面が非常にラクになります。二人で使用しても水道光熱費が2倍にはなるわけではないので、一人当たりの金額は低く抑えられます。
生活費を折半することで浮いたお金を家賃に回し、広くて新しい部屋に住むというのもひとつの選択肢です。3LDKや4LDKを借りるとしても、一人当たりの家賃は同エリア内の1Kや1DK程度で済むことも珍しくありません。2LDKや3DK程度の広さの部屋ならば家賃はさらに抑えられますので、あえて部屋のランクを落として貯蓄に回すのもよいでしょう。
賃料の予算を決めるときのポイント

誰もが上質な物件に住みたいと考えますが、支払える家賃には限りがあります。自分の収入で支払える家賃の予算を決めるためには、どのような点を考慮すればよいのでしょうか。
収支シミュレーションをする
家賃に使える金額を決めるためには、収入に対する支出の内訳をシミュレーションするのがおすすめです。一人暮らしでは収入のすべてを家賃に費やすことはできません。家賃のほかにも必要な生活費などの支出を計算し、家賃に使える金額を逆算するとよいでしょう。
上の項で紹介した一人暮らし・二人暮らしの生活費の割合では、一人暮らしでは収入の約30%、二人暮らしでは20%強が家賃に充てられていました。
しかし、上記は全年収帯の平均値であり、収入によって家賃に充てている比率は変わります。またそれぞれの項目に充てられる金額は世帯ごとのライフスタイルによって変わりますので、あくまで各支出額の参考値としてください。
ライフプランを設計する
長い人生の中で、転機となるライフイベントは何度も訪れます。就職や転勤、結婚や出産といったイベントのたびにまとまったお金が必要になるため、将来を見据えた資金の確保は非常に重要といえるでしょう。いざイベントが起きたときに慌てないよう、なるべく早いうちに将来を見据えたライフプランと連動した資金計画を立てておくのがおすすめです。
家賃は毎月決まった金額を支払う必要がある固定費です。貯金の有効な手段としても「固定費の削減」が挙げられるように、特に家賃の見直しは長期間に渡って支出を抑える効果が期待できます。
無理に狭くて古い家を選ぶ必要はありませんが、計画的に貯金をするためにも収入に見合った家賃で借りられる家を選ぶように心がけましょう。

高齢化の進行によって年金だけでは2000万円程度の老後資金が不足するといわれています。仮に家賃を毎月3万円抑えることができた場合、30年で1080万円と目標の半分を貯めることができます。無理なく老後資金を貯めるためにも、固定費に占める割合の高い家賃をうまく抑えましょう。
まとめ
家賃の目安は手取り金額の1/3程度といわれていますが、昨今では物価上昇や税率のアップなどの影響を受け、1/4程度に抑えるのが望ましいと考えられます。
家賃は家計の中でも大きな割合を占める固定費であるため、低く抑えることが貯蓄額のアップに繋がります。自分の手取りの中で選べる最高の部屋に住むのか、将来を見据えて家賃を抑えるかは選択次第です。将来に向けたライフプランを考えながら、自分のライフスタイルにあった部屋を選びましょう。
監修者プロフィール
 監修者
監修者
- 矢野 翔一
- 関西学院大学法学部法律学科卒業。有限会社アローフィールド代表取締役社長。保有資格:2級ファイナンシャルプランニング技能士(AFP)、宅地建物取引士、管理業務主任者。
不動産賃貸業、学習塾経営に携わりながら自身の経験・知識を活かし金融関係、不動産全般(不動産売買・不動産投資)などの記事執筆や監修に携わる。