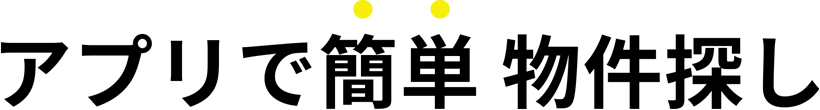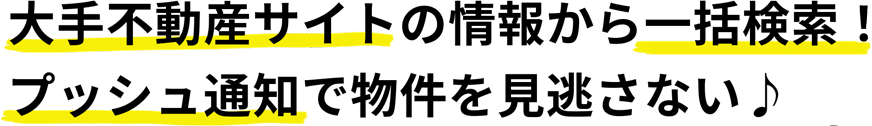住宅ローンを見る
住まいのコラム
不動産取得税とは?いくら払う?
金額の目安・計算方法や軽減措置について
最終更新日:
 監修者
監修者
- 亀梨 奈美
- 不動産ジャーナリスト/株式会社real wave代表取締役
- 不動産取得税とはどのような税金ですか?
- 不動産を取得した際に課せられる税金で、不動産の課税標準額と税率をもとに算出されます。納付時期は不動産を取得して約半年後で、一定条件を満たす場合は、申告することで控除の適用を受けられる場合があります。控除が適用されるかどうかで、納税額が数十万円単位で変わるため注意しましょう。
土地や建物といった不動産を取得した際に課せられるのが、不動産取得税という税金です。
不動産を取得した際に一度だけ納める税金という性質上、あまり馴染みがない人も多いでしょう。しかし取得した不動産の評価額によって、数十万~数百万円を納める必要があるため、どれくらいの支払いが発生するかを知っておく必要があります。
今回は不動産取得税の計算方法や、軽減税率・控除が適用される条件などについて、2024年時点での最新情報をお伝えします。
不動産取得税は土地や建物購入でかかる税金

不動産取得税は、新しい家や土地を購入した際に一度だけ発生する税金です。不動産取得税は地方税のため、納付先は購入した不動産がある都道府県になります。
不動産の購入のみならず、贈与や建築、等価交換などで不動産を取得した際にも課税されますが、相続時は課税されません。
不動産取得税の計算方法

不動産取得税は、課税標準額と税率によって算出されます。
不動産取得税額=課税標準額×税率
課税標準額は、原則として不動産の固定資産税評価額に基づいており、通常は時価(物件を購入した時の価格)よりも低くなります。目安としては、土地の場合は時価の70%程度、建物の場合は50〜60%程度です。
税率は土地・建物共に原則4%ですが、2027年3月31日までの取得に限り、いずれも税率3%の軽減税率が適用されます。また宅地に関しては、土地の評価額の2分の1を課税標準額として計算します。
| 本則 | 軽減税率 (2027年3月31日取得分まで) |
|
|---|---|---|
| 宅地 | ×4% | 評価額×1/2×3% |
| 住宅 | ×4% | ×3% |
不動産取得税の軽減措置

不動産取得税には、軽減税率のほかにも、一定の要件を満たす住宅を購入する場合の軽減措置があります。
建物の軽減措置
建物においては、新築か中古かによって控除額が異なります。
新築住宅の場合の控除額上限は1200万円が基本で、2026年3月31日までに取得した認定長期優良住宅の場合は1300万円が上限です。
中古住宅の場合は、新築された日(登記された日)ごとに控除額が以下のように定められています。
| 中古住宅の新築日 | 控除額 |
|---|---|
| 1997年4月1日以降 | 1200万円 |
| 1989年4月1日~1997年3月31日 | 1000万円 |
| 1985年7月1日~1989年3月31日 | 450万円 |
| 1981年7月1日~1985年6月30日 | 420万円 |
| 1976年1月1日~1981年6月30日 | 350万円 |
| 1973年1月1日~1975年12月31日 | 230万円 |
| 1964年1月1日~1972年12月31日 | 150万円 |
| 1954年7月1日~1963年12月31日 | 100万円 |
また、控除の適用を受けるためには、下記の条件をすべて満たしていることが条件となりますので、併せて押さえておきましょう。
・個人が自己の居住用に取得した住宅であること
・床面積が50㎡以上240㎡以下であること
・新耐震基準に適合していること
土地の軽減措置
住宅用の土地を取得した場合も、不動産取得税の算出時に控除を受けられる場合があります。
控除額は以下の(1)と(2)のうち、いずれか高い方が適用されます。
(1)4万5000円
(2)土地1㎡あたりの価格×住宅の床面積の2倍(1戸あたり上限200㎡)×住宅の取得持分×3%
適用要件は、土地に建っている物件が不動産取得税の軽減措置の対象であることを前提に、新築と中古それぞれ異なります。
新築の場合
土地を取得後3年以内に、当該土地上に住宅が新築されていること
ただし、次の①②のいずれかに該当する場合に限る。
| 土地を先に取得した場合 | 新築住宅を先に取得した場合 (同時取得を含む) |
|---|---|
| ①土地の取得者が、住宅の新築までその土地を引き続き所有していること | ①住宅を新築した方が、新築後1年以内にその敷地を取得していること |
| ②土地の取得者からその土地を取得した方(譲渡の相手方)が、住宅を新築したこと | ②新築未使用の住宅とその敷地を、新築後1年以内(同時取得を含む。)に同じ方が取得していること |
中古の場合
| 土地を先に取得した場合 (同時を含む) |
中古住宅を先に取得した場合 |
|---|---|
| 土地を取得した方が、当該土地を取得した日から1年以内(同時取得を含む。)にその土地上の中古住宅を取得していること | 中古住宅を取得した方が、当該住宅を取得後1年以内にその敷地を取得していること |
軽減を受けるには申告が必要
不動産取得税の軽減措置を受けるためには、取得した不動産のある地域のある管轄の税務署に、不動産取得税申告書を提出・申告する必要があります。
新しく不動産を新居に入居してから数ヵ月後に納税通知書が送られてきますが、申告していないと軽減前の税額が記載されています。
申告期限は各自治体の条例で定められており、都道府県ごとに異なりますが、不動産取得後30日以内または60日以内となっているケースが多いようです。
申告をしなければ控除が適用されず損をしてしまうため、必ず期限内に手続きを完了させましょう。

軽減措置の申告は原則的に納税前にする必要がありますが、申告をし忘れた場合も還付請求が可能です。ただし、いつまでも還付が受けられるわけではなく「5年以内」という期限があるため注意しましょう。
不動産取得税の計算シミュレーション

それでは実際に、固定資産税評価額3000万円の新築戸建を購入した場合を例にして、不動産取得税計算のシミュレーションをしてみましょう。
軽減措置なしの場合
まずは不動産取得税の軽減措置を利用しない場合です。
不動産取得税の計算方法をおさらいすると、物件の課税評価額に一定の税率をかけて算出します。
ここで言う課税評価額は3000万円、税率は2024年3月時点での取得の場合は、軽減税率が適用されるため3%で計算します。
3000万円×3%=90万円
軽減措置が適用されない場合の不動産取得税は90万円です。
軽減措置あり場合
次に、軽減措置が適用される場合の不動産取得税を計算します。
2024年3月に新築戸建を購入する場合、1200万円の控除を受けられます。
(3000万円-1200万円)×3%=54万円
軽減税率が適用された場合の不動産取得税は54万円で、適用されない場合と比較して36万円もの差が出る計算です。
不動産取得税はいつ納税すればいいの?

不動産取得税は、決められた時期に所定の方法で納付する必要があります。
納税時期
不動産取得税の納税通知書は、不動産を取得して6ヵ月から1年の間に届きます。毎月7日前後に管轄の税務署から発送され、発送月の月末が納付期限というのが一般的です。
納税方法
不動産取得税の納付は、税務署や金融機関、郵便局での入金のほかにも、自治体によってはクレジットカードなどのキャッシュレス納税に対応しているところもあります。
詳しくは対象の自治体にお問い合わせください。

印紙税や登録免許税は不動産の売買時や引き渡し時に課税されますが、不動産取得税は不動産を取得し、少し落ち着いたタイミングで納税通知書が届くため、その存在を忘れてしまいがちです。十数万円から数十万円におよぶ可能性のある税金ですので、あらかじめ納税資金を準備しておきましょう。
まとめ
不動産取得税は、物件を購入して半年程度経ったタイミングで納税通知書が届き、期日までに納付しなければなりません。
あらかじめまとまった支出に備えておくだけでなく、控除の対象になる物件に関しては、必ず税務署への申告を行うことが重要です。
※本記事に掲載されている不動産取得税の軽減措置については、2024年3月時点の調査に基づき、掲載しております。最新の適用期限等は変更となっている可能性があります。最新の情報は、国土交通省や地方自治体のサイト等でご確認ください。
監修者プロフィール
 監修者
監修者
- 亀梨 奈美
- 株式会社real wave代表取締役。大手不動産会社退社後、不動産ライターとして独立。
2020年に株式会社real wave設立。不動産全国紙の記者として、不動産会社や専門家への取材多数。
「わかりにくい不動産を初心者にもわかりやすく」をモットーに執筆している。