礼金とは?
敷金との違いや金額相場、交渉のポイントを簡単に解説
最終更新日:
 監修者
監修者
- 三輪 歩己
- 不動産鑑定士/宅地建物取引士/日本証券アナリスト協会検定会員(CMA)/相続診断士/J-REC公認不動産コンサルタント
- 礼金ってなに?敷金との違いは?
- 礼金は賃貸借契約時に支払う費用のひとつで、家賃の1~2ヵ月分が相場です。礼金には貸主への謝礼の意味があり、一度支払うと返還されない点が敷金との違いです。敷金は貸主に担保として預けておくもので、退去時の原状回復の際や家賃滞納時に使用されますが、礼金と違って、残金があれば退去時に返還されます。
賃貸物件を借りるときにはさまざまな初期費用がかかりますが、そのひとつに礼金があります。礼金とは何に対して払う費用なのか、相場や金額交渉は可能なのかなど、気になる人もいるでしょう。
この記事では、礼金の意味や相場のほか、礼金なし物件の特徴や礼金の金額交渉の方法などを解説します。
礼金とは賃貸物件を借りる際の初期費用のひとつ

礼金とは賃貸借契約時に支払う初期費用のひとつで、大家さんなど貸主に対して謝礼の意味を込めて渡すものです。しかし、現在は昔のように大家さんと入居者のあいだに密な関わりがあるケースは少なく、物件によっては、直接顔を合わせる機会がほとんどないことも珍しくありません。そのため、現代における礼金は、本来の謝礼の意味を込めたものというよりは、慣習として残っている側面もあります。
礼金と敷金の違いは?礼金は返ってくる?
敷金も、賃貸借契約時に貸主に支払う費用ですが、礼金と敷金には、返還があるかどうかの違いがあります。礼金は謝礼として支払うため、一度支払うと返還されません。
一方の敷金は、退去時のクリーニング代などの原状回復や家賃滞納時に使うために、貸主に担保として預けておくもので、残金があれば退去時に返還されます。
敷金とは?礼金との違いや返金の有無、なしの場合のデメリットを解説
礼金はいつ払う?
礼金は、敷金を含むほかの初期費用と同様に、賃貸借契約時に一括で支払います。支払うのは初回契約時の1回だけで、家賃や更新料のように、毎月や更新の都度支払う費用ではありません。
礼金の相場は家賃の1~2ヵ月分

礼金として支払う費用の相場は、家賃の1~2ヵ月分です。
国土交通省の調査によると、2022年度に入居者から貸主に支払われた礼金の月数で最も多かったのは「家賃の1ヵ月分」で69.4%、次に多いのが「家賃の2ヵ月分」で17.7%となりました。
同調査で、賃貸物件を借りる際に礼金を支払ったかどうかを調べたところ、「礼金なし」が46.5%、「礼金あり」が44.8%でした。礼金なしの物件のほうが、やや多いことがわかります。
出典:国土交通省 住宅局「令和4年度 住宅市場動向調査報告書」
この調査によると、賃貸物件に入居する45%以上の人が礼金を支払っておらず、礼金の支払いがある場合は、賃料の1ヵ月分が相場であることがわかります。
礼金なしの物件もある
国土交通省の調査で、礼金の支払いがなかった人が46.5%もいたように、現在は、礼金なしの物件も多くなっています。賃貸物件の入居率を高めるために「礼金なし」を打ち出して、入居者の初期費用の負担を抑えている物件もあるためです。
また、UR(都市機構)の賃貸住宅や、住宅供給公社などが貸主となる物件も、礼金を支払う必要がありません。この物件は仲介手数料や更新料もなく、初期費用を抑えることができます。
UR賃貸の住宅の概要や申し込み条件ついてはこちらでも詳しく解説しています。
UR賃貸住宅とは?ふつうの賃貸と家賃は違う?メリット・デメリットを解説
 監修者
監修者
礼金の性質については諸説ありますが、大家さんに対して賃貸借契約締結のお礼という意味があります。礼金の相場としては家賃の1~2ヵ月ですが、借手の初期費用の負担を軽くするために「礼金なし」にするケースもあります。初期費用を抑えるために、礼金なしであることを条件にして物件を探す方も多いようです。
礼金なし物件のメリット・デメリット
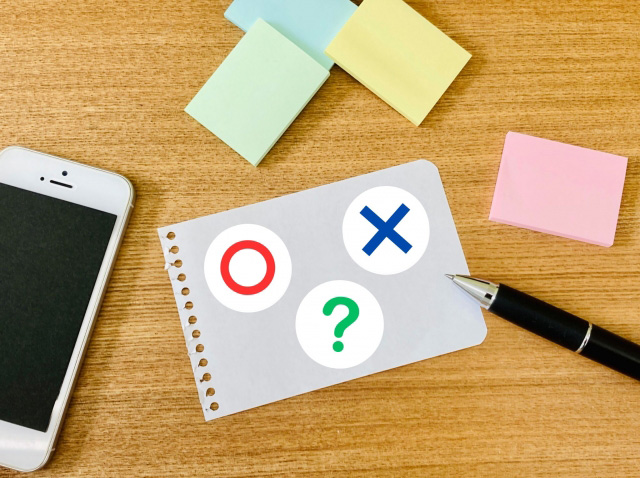
初期費用が抑えられる礼金なし物件は、賃貸物件を探す人にとって魅力的です。しかし、礼金なし物件はメリットだけでなくデメリットもあります。それぞれ確認しておきましょう。
礼金なし物件のメリット
引越しの際には、礼金や敷金などの初期費用以外にも、引越し料金や家具・家電の購入など、何かと出費が多くなるため、初期費用はできるだけ抑えたいところです。礼金なしの物件は、賃貸借契約時に負担する初期費用を大きく抑えられる点がメリットです。
たとえば、家賃が6万円の賃貸を借りる場合は、礼金が家賃1ヵ月分なら6万円、2ヵ月分なら12万円を負担しなければなりません。礼金は敷金と違い、退去時に差額が返ってくることもない費用です。家賃が高くなるほど、初期費用の礼金の負担感は増していきます。
礼金なし物件のデメリット
礼金なし物件の中には、空室を避けるためや、長く空室であるために礼金を0円にして、入居者にメリットを提示しているケースもあります。空室の期間が長い背景には、近隣トラブルがあった、駅から遠い、設備が古い、築古、近隣の家賃相場よりも賃料が高いといった理由があるかもしれません。
空室の期間が長い場合は特に、その理由を管理会社に確認することをおすすめします。設備の古さや築古であることは、内見時にしっかりと確認して気にならなければ、問題ありません。
礼金・敷金なし物件の注意点
礼金だけでなく、敷金もなしの物件も一部あります。一見お得に思えますが、こうした物件は、敷金と礼金に相当する金額が家賃に上乗せされていることもあるため注意が必要です。長く住むほど、敷金・礼金を支払った場合より、結果的に高くなってしまうことがあります。礼金・敷金なしの物件は、家賃が相場よりも高くないか確認してみましょう。
また、敷金という名前ではないだけで、退去時のクリーニング代として別途、入居者の負担費用が設定されているケースもあります。その場合、実質的な負担としては、敷金1ヵ月分を預けるのと変わりません。
さらに、敷金・礼金ゼロの物件は、短期解約の違約金の規定の有無も確認する必要があります。短期解約の違約金とは、たとえば1年未満で解約するなら賃料2ヵ月分を、2年未満で解約するなら1ヵ月分を、退去時に違約金として支払うといった規定です。
短期間の入居を予定して初期費用を抑えて契約できたとしても、退去時に高額な請求がある可能性があります。短期間で退去する予定がある場合は、規定の有無の確認を忘れずに行ってください。
 監修者
監修者
礼金ゼロ、敷金ゼロのいわゆる「なしなし物件」については、注意しなければならない場合もあります。周辺の家賃相場より高く設定されていることから、敷金と礼金がゼロになっているようなこともあります。初期費用を抑えることにとらわれず、長期的な視野から問題がないか確認したうえで契約しましょう。
礼金の金額は交渉できる?

礼金は一度支払うと戻ってこない費用のため、できるだけ支払額を抑えたい人もいるでしょう。実は、礼金は、物件によっては契約前に金額の交渉をすることが可能です。
ここでは、礼金の金額の交渉をしやすい物件の特徴や、交渉をする相手について紹介します。
礼金の交渉がしやすい物件
礼金の金額交渉をしても、すべての物件で減額してもらえるわけではありません。比較的礼金の金額交渉に成功しやすい物件には、次のような特徴があります。
<礼金の金額交渉がしやすい物件の特徴>
・相場(家賃の1~2ヵ月)よりも礼金が高い物件
・駅から遠い、設備が古い、築古など、借手が避けがちな条件のある物件
・長いあいだ空室になっている物件
空室があり常に入居者を募集している物件や、駅から遠いなど借り手に人気のない条件のある物件は、比較的礼金の交渉がしやすい傾向があります。
一方、駅から近い、新築または築浅などの好条件で人気の物件は、礼金の交渉は難しくなります。
礼金の交渉をする相手
最終的に礼金を減額するかどうかを判断するのは貸主(大家・オーナー)ですが、入居希望者が礼金の金額を交渉する相手は、基本的には物件を仲介する不動産会社です。
初期費用を抑えたい理由を相談しつつ、礼金の金額交渉の可能性があるか、担当者に質問してみるとよいかもしれません。
 監修者
監修者
礼金の金額を交渉するのにもポイントがあります。多くの場合で、家賃が高い、駅から遠い、建物や設備が古いなど、賃貸物件としてデメリットがあることから、結果として長期間空室になっている物件が、礼金の金額を交渉しやすい物件です。なかなか空きがでないような人気の物件は、礼金の金額交渉は難しいでしょう。
賃貸物件の初期費用

賃貸物件の初期費用とは、賃貸物件に入居する際にかかる費用のことです。礼金をはじめ、賃貸借契約に必要な初期費用には、主に次の6項目があります。
1.敷金
敷金は、退去時の原状回復費用や家賃を滞納した際にあてられるお金で、残金があれば退去時に返金されます。相場は家賃の1~2ヵ月分で、物件によっては敷金なしの場合もあります。
2.礼金
礼金は、大家さんなど貸主に部屋を借りる謝礼として支払うもので、返還されません。相場は家賃の1~2ヵ月分で、物件によっては礼金なしの場合もあります。
3.入居月の日割り家賃
入居が月の途中だった場合、1ヵ月分の賃料をもとに、入居開始日から入居月の最終日までの日数で割った家賃を支払います。
4.翌月家賃(前家賃)
翌月家賃は、入居前に入居月だけでなく、その翌月の家賃も前払いするための費用です。
5.火災保険料
賃貸借契約では、火災保険への加入が義務付けられています。火災や水漏れ、室内設備の破損の保証など、物件が指定する契約プランによって金額は異なりますが、1万~2万円程度が相場です。
6.仲介手数料
仲介手数料は、賃貸借契約における仲介業務(物件の内見や契約手続きなど)を担当する不動産会社に支払う費用です。相場は家賃の0.5~1ヵ月分+消費税ですが、中には仲介手数料半額や無料のキャンペーンを行う不動産会社もあります。
そのほかに、前の住人が使用していた鍵を新しいものに交換するための鍵交換の費用を、入居者が負担する場合があります。ディンプルキーなど防犯性の高い鍵に変更する場合、費用が高くなります。相場としては1万5000~2万5000円程度です。
また、物件によっては、連帯保証人の代わりに家賃保証会社への加入を必須としていることもあります。費用としては、保証会社によって異なりますが、おおむね家賃の0.5~1ヵ月分です。
賃貸物件の初期費用を抑えるコツ
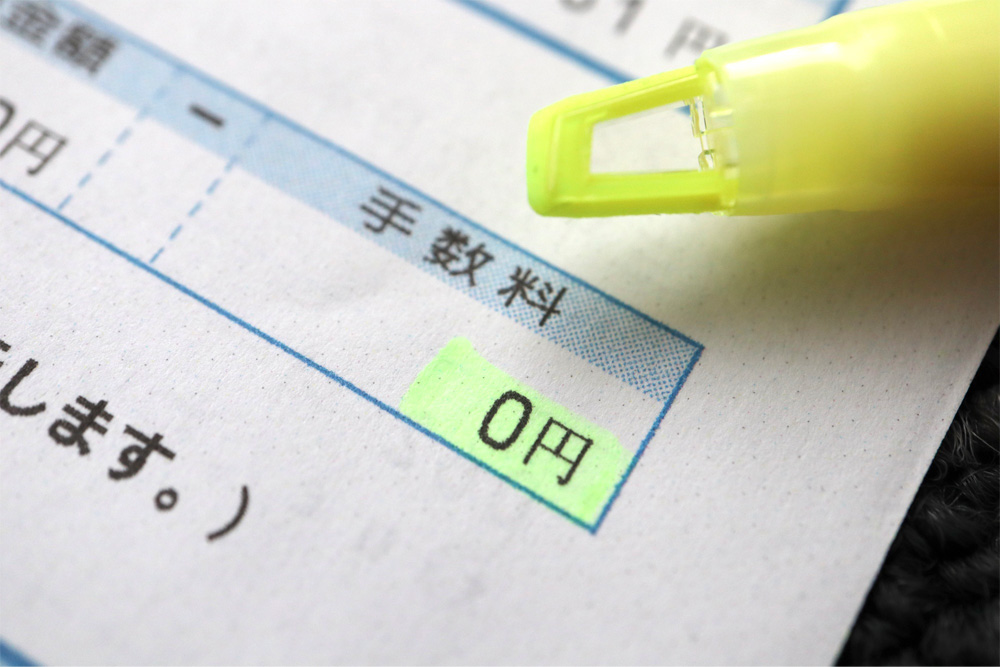
前述したとおり、賃貸借契約時の初期費用には、礼金以外にもさまざまな費用があります。続いては、初期費用全体の金額を安くするコツを見ていきましょう。
フリーレント、敷金・礼金ゼロのキャンペーンを狙う
フリーレント物件とは、入居後の一定期間、家賃がかからない物件のことです。共益費や管理費は支払う必要がありますが、入居月の日割り家賃や翌月家賃(前家賃)の支払いがなくなれば、通常の賃貸借契約と比較して初期費用を大きく抑えられます。
また、物件によっては期間限定で敷金・礼金ゼロなどのお得なキャンペーンを実施していることもあります。物件探しの期間に余裕があるなら、不動産会社や不動産情報サイトのキャンペーンを狙うのもひとつの方法です。
仲介手数料の安い不動産会社を利用する
仲介手数料が家賃の半額以下、または無料であることで他社と差別化をしている不動産会社もあります。初期費用を抑えるために、仲介手数料の安い不動産会社に依頼することを検討してもよいかもしれません。
また、敷金・礼金ゼロのキャンペーンと同様に、一時的に仲介手数料が無料になるキャンペーンが行われる場合もあります。
不動産会社の閑散期に物件を探す
不動産会社の繁忙期は12月から4月上旬で、この時期に仲介手数料などの初期費用が下がることはあまりありません。4月下旬から11月の閑散期に物件探しをすると、初期費用が抑えられるキャンペーンが行われていたり、不動産会社と初期費用の交渉ができたりする可能性が高まります。
クレジットカード払いができる不動産会社を選ぶ
クレジットカード払いができる不動産会社はあまり多くないものの、ゼロではありません。初期費用をクレジットカード払いにできれば、金額が大きいためポイントやマイルなどを一気に貯めることができます。
初期費用の節約ではないものの、クレジットカード払いができれば、現金払いよりもお得感があるでしょう。
まとめ
礼金は、賃貸物件を借りる際に必ず発生するものではなく、物件によってはゼロになったり、減額の交渉をしたりすることもできます。礼金の役割や、礼金なしのメリット・デメリットを把握したうえで、礼金なし物件も含めて物件を検討してみましょう。
また、賃貸借契約では、礼金のほかにもさまざまな初期費用がかかります。初期費用の内訳は物件ごとに異なるため、費用に違和感がないか、契約前にしっかりと確認することをおすすめします。
監修者プロフィール
 監修者
監修者
- 三輪 歩己
- 不動産鑑定士、宅地建物取引士、日本証券アナリスト協会検定会員(CMA)、相続診断士、J-REC公認不動産コンサルタント。
約20年間の鑑定・宅地建物取引業の経験を活かし、2020年に不動産パートナーズ株式会社を設立し、代表取締役に就任。同社では、不動産鑑定業・宅地建物取引業に加え、不動産専門の相続診断士として活動を行う。
















